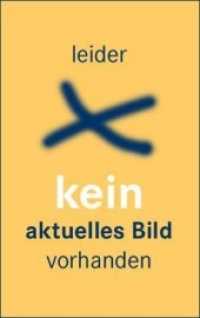内容説明
「運命」、「喜びの歌(交響曲第九番)」など、数あるクラシック音楽のなかでも日本人にはとくになじみの深い音楽家、ベートヴェン。ロックに通じるエンターテイメント性、カリスマ性、パフォーマンスの妙など、大胆な角度から楽聖ベートーヴェンとその音楽を解剖し、新たなベートーヴェン像を描く。予備知識や常識を取り払ってしまえば作為の音の組み合わせに過ぎない「音楽」とは何か。そしてなぜ私たちは西洋音楽が好きなのか。ベートーヴェンの考察を軸に、「音楽を聴く」体験の原点に立ち返り、音を楽しむことを捉えなおす試み。
目次
序、または無音という名の音
第1部
ノイズとしてのパパ・ハイドンまたは蘭学事始
差別する耳、または乱楽事始
レコード店訪問、または音楽歴史地図
Kちゃんのコンサート体験、または真夏の夜の夢
Jさんのコンサート体験、または主題と変奏
第2部
架空のベートーヴェン交響曲全集、または暗くなるまで待って
消費者X氏のベートーヴェン像、または時計じかけの俺んち
交響曲第一番ハ長調、またはいの一番
交響曲第ニ番ニ長調、または第二の生
交響曲第三番変ホ長調『エロイカ』、または第三の男
交響曲第四番変ロ長調、または読んで字の如く
交響曲第五番ハ短調、または誤解の五感
交響曲第六番イ長調『田園』、または第六感
交響曲第七番イ長調、または第七の封印
交響曲第八番ヘ長調、または大八車
交響曲第九番ニ短調、または大工
X氏あとがき
著者あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1959のコールマン
54
☆3。う~~~ん。タイトルから期待した内容とは程遠い。論、というよりエッセイ・・・いやちょっとした殴り書きのような文章。2章からなる少女とおじさんの架空コンサート体験記なんかいらんでしょ。これ。それより最初の3章の内容をもっと深掘りしろよ。肝心のベートーヴェンに関する記述もp71になってようやく出てきて、それも「消費者X氏」が書いた、なんていらん設定をしている。取り上げた作品も交響曲のみ。しかも第2番と第8番を最高傑作と持ち上げている。あのね~~素直に書けばいいものを・・・。↓2022/08/13
-
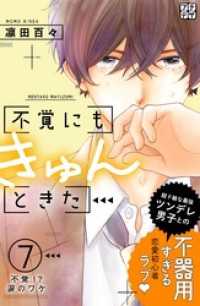
- 電子書籍
- 不覚にもきゅんときた プチデザ(7)