- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
・欧米の名門大学では、なぜ「古典的教養(リベラルアーツ)」が重視されるのか。
・なぜ、リベラルアーツが米国エリート教育の原点となったのか。
・プラトン、アリストテレスの思想・哲学を現代人が学ぶ意味とは何か。
グーグルやアマゾンも重視する「西洋的教養」の真髄を凝縮した意欲作。
目次
序 章 なぜ米国の一流大学はリベラルアーツを重視するのか
第1章 黎明期のギリシャ ~リベラルアーツの土壌はこうして生まれた
第2章 ヘロドトス『歴史』で知るヨーロッパの原点
第3章 トゥキュディデス『戦史』が描く衆愚のギリシャ
第4章 プラトン『国家』が掲げる理想主義
第5章 アリストテレス『ニコマコス倫理学』が掲げる実践主義
第6章 アリストテレス『政治学』が描く現実的国家論
第7章 ローマの繁栄から中世キリスト教支配の時代
第8章 「西洋」優位の時代の幕開け ~ルネサンスから近代まで
終 章 〝超大国〟アメリカで磨かれたリベラルアーツ
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
95
有名なコロンビア大学でのリベラルアーツ教育の概要を紹介した一冊である。タイトルに「ギリシャ・ローマ」とあるが、殆どの紙幅がギリシャに費やされているのは、「リベラルアーツの基本はヘレニズム哲学である」という主張が徹底しているからだろう。でも、アウグスティヌスを新プラトン主義で捉えたり、トマス・アクィナスの神学の根拠をアリストテレスに求めるというのは容認するとしても、キリスト教の絶対的な教義である復活や最後の審判まで、「国家」の「エルの物語」と結びつけてしまうというのは、少し牽強付会に過ぎると感じるのだが…。2021/07/06
33 kouch
50
教育とは視力を与えることではなく、視界を変えさせること、というのがインパクト強かった。 「リベラルアーツ」なんて言葉、自分が学生のときは聞かなかったが。一瞬プロレス技かなにかと思った…。直訳だと一般教養教育。固定概念を廃し"現代人が自由に生きていくための手段"というほうが意味が近い。「〇〇で必要だから学ぶ」ではなく「なにが世の中で必要なのかを学ぶ」。自分が読書をする理由もここにある。ギリシャ・ローマ時代に由来する、これこそ真の学びだと思う。 本書はギリシャ・ローマの歴史や宗教の復習にもなる。2023/10/24
おさむ
35
期待して読んだのだが、高校時代の世界史の教科書を読んでいるかのような錯覚に陥った(もちろん山川出版社)。ヘロドトスの歴史や、トゥキディディスの戦史、プラトンの国家、アリストテレスの政治学‥‥。題名しか暗記していなかった名著の詳細なあらすじが紹介されている点がキモといえば、キモか。これら名著を知っていて役立つのは、欧米の書物や記事、論文などに使われる格言や比喩、言い回しなどの理解が進むという点。最近の例でいえば、「トゥキディディスの罠」ですかね。2021/06/07
まると
26
ここに書かれているのが教養だとしたら、私はそれをほとんど学ばずにきた人間なのだと痛感します。古代ギリシャで生まれた人類の英知がルネサンスで復興し、啓蒙思想につながるまでの壮大な流れをしっかりと認識したことはなかった。ただでさえ読まなければならないと思っている本が山積みなのに、それがさらに積み重なって茫然自失の状態です。まずは表紙のラファエロの絵画「アテナイの学堂」にも描かれているプラトン、アリストテレスから始めてみようか。全ての読破は無理だけど、少しずつでも読み進めたいと決意を新たにさせられる一冊でした。2021/07/02
ta_chanko
20
ホメロス・ヘロドトス・トゥキディデス・ソクラテス・プラトン・アリストテレス。古代ギリシャで生まれた学問・哲学がアレクサンドロスの東方遠征によりオリエント全体へ(=ヘレニズム文化)。その後、ローマ帝国→ビザンツ帝国、イスラーム世界へ。西欧ではアウグスティヌス・トマス=アクィナスがキリスト教との整合性を確立。ヘレニズム文化はルネサンス期にビザンツやイスラームから西欧へ逆輸入。マキャベリ・ホッブズ・ロック・ルソー・アダム=スミス・JSミル・マルクス・ダーウィンの近代思想が生まれた。壮大な知の体系。2021/07/02
-

- 電子書籍
- comic Berry's 再愛~次期…
-

- 電子書籍
- リベンジ~最強剣神の復讐~【タテヨミ】…
-
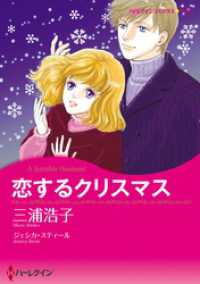
- 電子書籍
- 恋するクリスマス【分冊】 10巻 ハー…
-
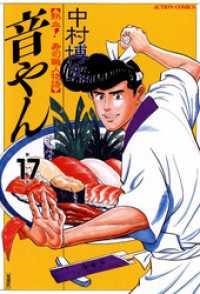
- 電子書籍
- 音やん 17巻
-
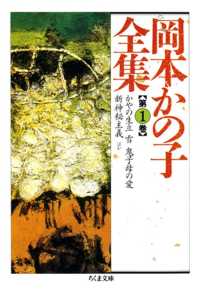
- 電子書籍
- 岡本かの子全集(1) ちくま文庫




