- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
近代化によって日本の農村生活は大きく変わった。農村社会が瓦解すれば日本社会そのものが瓦解するとの危機感を抱いた農村社会学者は、20世紀初めからその移り変わりを長く記録してきた。本書はその記録を読み解くことで、日本の各地域の農村のあり方、農村における「家」と「村」の歴史を再構成する。「同族団」と「自然村」のあり方、農村のタイプによる地域差など、ともすれば現在の我々が忘れ去ってしまいそうな農家・農村の姿を見いだしていく。日本農村社会学の総括。
目次
はじめに
Ⅰ 日本農村を見る視座
第一章 「同族団」とは何か
山村「石神」
モノグラフ調査
大屋S家
同族団
名子と作子
スケとユイ
集落の同族団支配
同族団支配の解体、そして農地改革
農地改革後の大屋の経営改革
旧仙台領江刺郡増沢村の同族団と組
第二章 「自然村」とは何か
「自然村」としての「部落」
「三重」の社会地区
江戸時代の村
日本農村の「伝統」的・「半封建」的理解
農村に見られる諸集団
有賀の「石神」と喜多野の「若宮」
「講」とは何か
「講」のさまざま──山形県庄内地方の事例
第三章 歴史を遡って──農村はどのようにつくられたか
中尊寺領骨寺村
新旧二つの同族団
なぜ村か
山村ならば
関東方面から、その後
「三信国境の村落群」
開発と土地領有、開郷当初の家と生活
焼畑作による粗放な農業と生活協同の体制
郷主連合(村落連合)とその変化
郷主の帰農
直系世代家族、非血縁奉公人の同居、長子単独相続
検地と百姓身分
「村」(藩制村)の成立と村内分家
郷村の鎮守と寺院、村の生活協同
「三信国境の村々」の諸特徴
有賀「石神」の同族団との比較
Ⅱ 日本農村の東西南北
第四章 日本農村の二類型──東北型と西南型
「日本社会民主化」の課題
東北型の事例・秋田県農村
本家と分家、マキという呼称
本家・分家関係は地主・小作関係
高利貸地主も家族主義的関係
東北型の特質
西南型の事例・岡山県農村
家族と本・分家関係
本・分家関係は「株内」、組と講
西南型の特質
類型論の問題意識
竹内利美の性別・年序別組織
第五章 まず西へ
西日本に視線を移して
宮座と同族
親方子方と講組結合
「最寄」と「株内」──京都府綾部市
株の成立と変化
「虫供養」、地付きの信仰と特定宗派との対立と習合
四国山村──田畑と家屋がスギに食いつぶされる
高齢者の山地農業と水資源の保全
第六章 南と北
視線を南に移して
大洋交易国家から農業国家へ
重視されるのは位牌継承
「村の単位としてのヤー」と「門中の単位としてのヤー」
門中の範囲とレベル
村落について
村々模合
視線を北に移して
アメリカ式大農場の失敗と小作制農場
自作地主型村落
砺波部落の変遷
農事組合型村落
小作制大農場
住民組合の実態
同郷者同士の結びつき
北海道の農村社会の特質
入会地・共有地の欠如、散居制の村落
「地主になるのだ」、農家の「投機的性格」
繰り返された小作争議
全農の支援、しかし敗北
第七章 「大家族」(家)制と末子相続
農村社会学と家
白川村大家族制の特徴点
硝生産
養蚕
ナギ畑と入会山利用
戸数変動の地域的特性
養蚕・糸挽と女性の役割
末子相続の研究
姉家督と末子相続、「末子相続」とは不定相続
門割制
西南九州の村落
「すっきりしない」鹿児島農民の生活基盤と村
鹿児島農家の相続慣行
鹿児島、沖縄と東南アジア
Ⅲ 「家」と「村」の歴史──再び東北へ
第八章 「家」と「村」の成立──近代以前
山形県庄内地方と稲作
一条八幡神社文書
小領主による開発
稲作集団の三重構造
「農民古風説」
庄内における「検地帳」と「宗門人別帳」
寛文の検地帳
「彦右衛門記録」
下人から「若勢」へ、「すけ」と「ゆい」
宝暦の検地帳
庄内の地主制
継承の家族関係──宗門人別帳
庄内の同族団
村の設定、村請制
協議・協力の組織としての村──水、草、人
神社と寺
設定された村と形成された村
第九章 「家」と「村」の近代──明治・大正・昭和
明治の変革と部落、村合併と神社
明治初期の家の後継者と婿取り
家族構成の動態
非後継者の運命
生活実態としての家
地主と明治町村制
地主と農事改良──川南の事例
乾田化と馬耕の導入──川北の事例
田区改正から耕地整理へ
耕地整理の問題点
小作農民の暮らし
川北、村契約による地主への要求、小作争議
農民組合運動から産業組合運動へ
交換分合と自作農創設
自作農創設の具体的方法
時代の趨勢としての自作農創設と交換分合
地主小作関係の諸相
終章 「家」と「村」の戦後、そして今
戦後の青年学級活動
青年意識のめざめと農協青年部運動
「四石のカベ」に共同化の試み
水稲集団栽培の形成
部落を場とする共同化
稲作各地の動向
集団栽培後の農家調査──夫婦家族連合としての家
女性調査の結果──家族内役割分担
もう一つの重要な問題──家の外での代表役割
村は今
直売所の女性たち
集落営農の動向
おわりに
引用文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
Arisaku_0225
Ex libris 毒餃子
天婦羅★三杯酢
おっきぃ
-
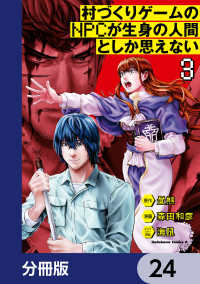
- 電子書籍
- 村づくりゲームのNPCが生身の人間とし…
-
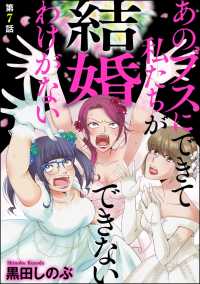
- 電子書籍
- あのブスにできて私たちが結婚できないわ…
-
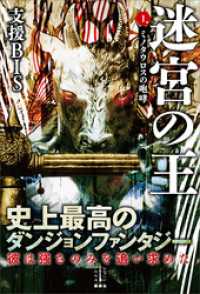
- 電子書籍
- 迷宮の王 1 ミノタウロスの咆哮 レジ…
-
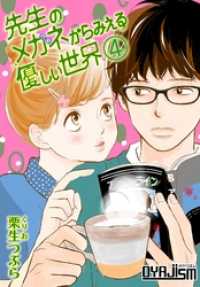
- 電子書籍
- 先生のメガネからみえる優しい世界 4 …





