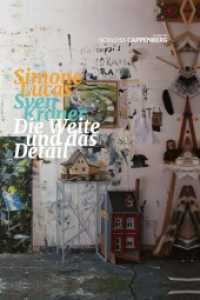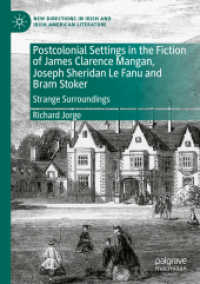内容説明
世界遺産から黙殺された島の「祈りの記録」。
250年以上も続いたキリスト教弾圧のなかで信仰を守り続けた「かくれキリシタン」たち。その歴史に光を当てようとしたのが、2018年に日本で22番目の世界遺産となった「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」だ。
ところが、PRのために長崎県が作ったパンフレットからは、「最後のかくれキリシタンが暮らす島」の存在がこっそり消されていた。
その島の名は「生月島(いきつきしま)」。
今も島に残る信仰の姿は、独特だ。音だけを頼りに伝承されてきた「オラショ」という祈り、西洋画と全く違う筆致の「ちょんまげ姿のヨハネ」の聖画……取材を進める中で、著者はこの信仰がカトリックの主流派からタブー視されてきたことを知る。一体、なぜ――。
第24回小学館ノンフィクション大賞受賞作。
文庫版解説・島田裕巳氏(宗教学者)
※この作品は単行本版として配信されていた作品の文庫本版です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まると
28
面白くも物悲しいレポート。長崎・生月島の「隠れキリシタン」は仏壇にも神棚にも祈りを捧げる、生業の農漁業と密接に絡んだ信仰を持っていた。ただ、それは異端にほかならず、遠藤周作が「古い農具」と軽侮したように、世界遺産にはそぐわないものだった。確かに実態は祟り信仰の一種でしかないのかもしれないが、400年以上伝承されたそのユニークな祈祷文化を知れば知るほど、未来に残すべき価値があるように思えてくる。著者もそこに問題意識を感じていたようだ。信仰とは何か、正統とは何か、世界遺産の虚実も含めて考えさせられる良書です。2022/09/04
あーびん
28
徳川政府の禁教令下で250年以上にわたって弾圧を逃れながら密かに守り続けてきた「かくれキリシタン」信仰が今も残る生月島。世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」登録によって脚光を浴びるはずが県のパンフレットからは島の名前が消されていた。それは土着の民俗宗教に変容した信仰なのか。それとも布教期の信仰形態を保存したものなのか。戦後にバチカンは島にわざわざ枢機卿を派遣し改宗をするように諭したが、島民はこれを拒み独自の信仰を続けることを選んだ。島民の信仰の現状と変化。遠藤周作も意外と厳しい目線。2021/06/27
よしじ乃輔
12
弾圧の中、写しは残さず(残せず)祈りの言葉と行事を口伝で受け継いできた結果、本来の教えから変質したように見える長崎生月の隠れキリシタン信仰。土着文化とも言える、守り切ってきた信仰は、カトリック本山から「復活」を勧められた結論はノーだった。近代になるにつれその信仰は負担になる程に、全生命をかけた祈りのかたちは、消えかけているのだろうか。信仰とは疑わないこと。その姿は信仰そのものでした。2025/02/04
ニコ
7
弱者の視点に立つと言って「沈黙」を書いたはずの遠藤周作が、隠れキリシタンへは共感の姿勢を見せなかった、と言うくだりが印象的。 私は長崎出身なので、大浦天主堂の信徒発見の逸話は馴染みがあり、感動したものだが、「そもそも教義さえ、当時の日本人は理解していなかった」という研究者もいるようで驚いてしまった。ならば弾圧され死んでいった信者は、なにに殉じたのか。 「ここからそう、天国は遠くない」というのも印象に残っていた逸話だったのだけど、それが創作と言われるとは…しかし、そこに納得できる部分もあり。歴史って難しい。2024/12/07
朔ちゃん
5
昔TVで観た「隠れキリシタン」のことが忘れられず手にとった。世界遺産から外され、資料にも載らない「生月島」こそ、かくれキリシタンの信仰そのものと著者は言う。生業(経済生活)と結びつき、サンジュワンさまという独特の信仰を持ち、1949に来日した枢機卿の前でもカトリック改宗はしなかったという。あとがきにあるように、祈りのかたちは世界遺産にならないが、伝えようとする意思が、現代にとって大いなる価値(遺産)になると思った。表紙は〈ちょんまげ姿の洗礼者ヨハネ〉である。聖画やオラショも神々しく興味深い。2021/07/12
-
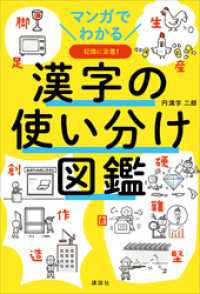
- 電子書籍
- マンガでわかる 漢字の使い分け図鑑