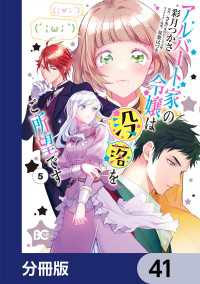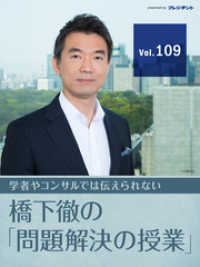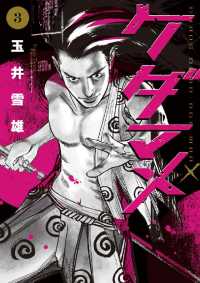内容説明
東日本大震災から一〇年、死者がどう扱われてきたかはメディアも遠慮がちにしか報じていない。だが未来に向けて、死者をはじめ震災への対応を記録に残さねばならないだろう。本書は、現場で対応に当たった行政担当者や寺院への聞き取り、自治体が発行した記録誌などから東日本大震災の過程を跡づける。さらに関東大震災、濃尾地震に際し政府や社会が死者に対しどう対応してきたかを史料で検証。長年にわたり災害社会史研究に携わってきた歴史学者が、震災と死者の問題を問いなおす。
目次
はじめに
Ⅰ 東日本大震災──死者の行方と避難の実態
第1章 消防団員の東日本大震災──「これはただ事ではない」
1 消防団員が直面した過酷な現実
2 瓦礫撤去、道路啓開、遺体捜索
3 これからの消防団
第2章 死者の行方
1 歴史に見る死者の行方
2 コミュニティーの核としての寺院の再興──名取市の場合
3 政教分離原則と宗教施設の再建支援
第3章 東日本大震災と仏教系メディア──死者をめぐる情報を中心に
1 分析の視角
2 仏教系メディアの報道姿勢と問題提起
3 各紙誌の記事に見る震災の諸問題と対応の経過
4 各紙に見る震災報道の特色
5 アンケート調査から見える宗教教団の現状と見通し
6 震災で寺院が直面した問題群
7 まとめにかえて
第4章 東日本大震災がもたらした死者に関わる問題群
1 津波災害がもたらした遺体処理問題
2 行政と葬儀社組合の協定書に基づく納棺支援業務
3 福島県の寺院の対応と厳しい現実
第5章 自治体記録誌の死者の記述について
1 記録誌が担う役割とその意味
2 仙台以北の津波激甚地──気仙沼市・石巻市・女川町・東松島市
3 仙台平野の被災地──名取市・岩沼市・亘理町・山元町
4 「検証報告」で明らかになった避難者行動と災害教訓──陸前高田市、釜石市
5 まとめにかえて
第6章 『大熊町震災記録誌』が伝える原発事故と住民避難
1 原子炉四基を抱える大熊町
2 東日本大震災の発生と住民避難
3 大熊町の復興計画と除染
4 まとめにかえて
Ⅱ 関東大震災──死者供養と寺院移転
第7章 関東大震災の寺院被害と復興──関東圏における真言宗智山派寺院の場合
1 これまでの研究
2 真言宗智山派寺院の被害
3 本山による被害寺院救済策
4 寺院復興に向けた仏教界の結束と提言
第8章 関東大震災と寺院移転問題──誓願寺塔頭と築地本願寺末寺の場合
1 震災と寺院移転
2 関東大震災における被害寺院
3 東京市における寺院移転──浅草田島町浄土宗誓願寺塔頭の場合
4 東京市における寺院移転の実際──浄土真宗築地本願寺末寺の場合
5 まとめにかえて
Ⅲ 濃尾地震──天野若圓と震災紀念堂
第9章 天野若圓の前半生
1 天野若圓とはどのような人物か
2 政界への進出
3 若圓、帝国議会議員となる
4 愛國協会の設立と『愛國新報』
第10章 濃尾震災紀念堂
1 濃尾地震
2 帝国議会の動き
3 震災紀念堂建立を目指す
4 まとめにかえて──震災紀念堂の「死亡人台帳」について
あとがき
参考文献
初出一覧
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme
takao
yokkoishotaro
かわくん
卓ちゃん