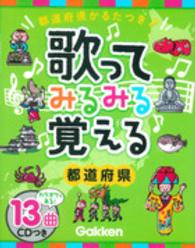内容説明
海辺はプランクトンの“大草原”であり魚の“ゆりかご”です.近代日本は,海辺の自然を失ってきました.「宝の海」を失った象徴的な例が有明海・諫早湾です.しかし,海の再生力は大きく,自然保全が社会経済的にも利益を生む実例もあるのです.有明海をよみがえらせて自然の価値をみつめることは,日本の再生にもつながるでしょう.
目次
年表 諫早湾干拓事業をめぐる主な出来事┴はじめに┴第一章 干潟がもたらす海の豊かさ┴第二章 日本の海のいま┴第三章 有明海の諫早湾でおこったこと┴第四章 海はよみがえる┴終章 日本の海辺を見つめ直す┴主な参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
11
干拓とは、堤防で海をせき止めて、水面下の海底を 陸地として利用すること。 しかし、人間がその分際を越えて、力ずくで 海の中に入っていくので、無理が生じる(39頁)。 社会が水俣病問題の歴史から学ばねばならないことは、 問題がおこってから対策を講じていては手遅れということ(44頁)。 農水省と長崎県は、農民と漁民の対立をつくった、と批判される(52頁)。 干潟が農地に代わったからである。 2014/04/05
konaka
2
3/52014/04/18
Ishida Satoshi
1
読了。先日セミナーでお会いした先生からいただいた本書。感謝。わずか70ページほどでありながら、諫早湾の再生、環境を取り戻すことがなぜ大切なのかということを生物学者である著者がわかりやすく解説してくれています。浅瀬、干潟に住む貝類、ゴカイ、カニなど底生生物が最も影響を受けやすく、人間活動の影響による変化を最も受けやすい存在であることがよくわかります。諫早湾干拓事業を事例に、宝の海を取り戻すためにできることは何か?、自然との向き合い方、人間と生き物の関係性について考えさせてくれる優れた入門書です。
-

- 電子書籍
- 試験にデル判例