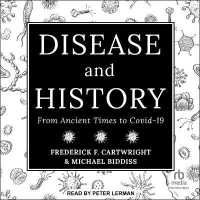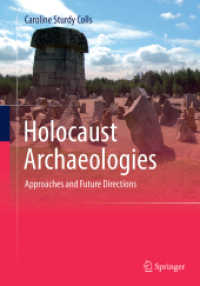内容説明
オンライン世界がいかにして「サイバーカスケード」を生み、「確証バイアス」を利用し、われわれを「分極化」するのか。民主主義の活力源である共有されるべき会話、経験、相互理解はいかにして危機に瀕するのか。現状を丁寧に解説したうえで、諸刃の剣インターネットを民主的な熟議に活用するための実際的、法的な改善点を提案する。
目次
はじめに
第1章 デイリー・ミー
アルゴリズムとハッシュタグ
二つの要件
なぜこれが問題なのか─暴力、党派心、自由
死と生
フェイスブックが望むこと
「私は恐ろしい。あなたはどう?」
先駆者と中間形態
『her/世界でひとつの彼女』
ソーシャルメディア
基準について一言
政治、自由、フィルタリング
取り上げない問題
第2章 類推と理念
公共空間という概念
街路と公園だけ?空港とインターネットのこと
“なぜ”公共空間なのか?接近、予期せぬ出会い、苛立ち
予期せず、望んでもいないこと
公共空間と認知されていない大衆メディア
二種類のフィルタリング
均質性、異質性、第一回連邦議会の話
多から成る一、ジェファーソン対マディソン
主権の二つの概念、ホームズ対ブランダイス
懐古趣味をともなわない共和主義
第3章 分極化
味、フィルター、投票
適切な偏向
情報過多、集団主義、多から成る一
コロラド州での実験
集団分極化
なぜ分極化か?
集団アイデンティティの計り知れない重要性
オンラインの集団分極化
ハッシュタグの国、ハッシュタグ考案者
ドナルド・トランプほか、政治家についてざっと触れる
断片化、分極化、ラジオ、テレビ
集団分極化は悪か?孤立集団内での熟議
孤立集団と公共圈
分極化しない場合および脱分極化
バランスのとれた情報の提示、バランスを欠いた見解
訂正が裏目に出るとき
よく知らない問題
理解する
第4章 サイバーカスケード
二種類のカスケード
野火のごとく広がる情報とティッピングポイント
政治的カスケードと混乱
噂とティッピングポイント
賛成票と反対票
殺人事件は何件?
分離、移行、統合
ツイッターでの同類性
友達とフェイスブック
事実、価値観、よいニュース
アイデンティティと文化
比較 討論型世論調査
危険と解決策
第5章 社会の接着剤と情報の拡散
経験の共有
連帯財
共有される経験の減少
消費者と生産者
公共財としての情報
隠喩としての飢饉、一つの説明
ニッチとロングテール
バイアスとエリート
ネットワーク化された公共圈
情報の拡散
第6章 市民
選択と状況、そして中国
選好の形成
限られた選択肢 キツネと酸っぱいブドウ
民主的な制度と消費者主権
全会一致と多数決ルール
消費のトレッドミル
民主主義と選好
第7章 規制とは何か?
共通の見解
矛盾した見方 あらゆる場所に規制と法律がある
インターネットの場合 歴史にかんする覚え書
インターネットの場合 ふたたび規制のこと
規制はどこにでもある、ありがたいことに
第8章 言論の自由
新しい見識?(そうではない)
言論の自由の二つの原則
言論の自由は絶対ではない
第一修正と民主的熟議
中立の形態
処罰と補助金
影響力があり、慎重な第一修正
第9章 提案
熟議ドメイン
礼儀正しさについての簡単な説明
殺菌剤としての日光
自発的自主規制と最高の慣行
補助金
マストキャリー 憲法論議
人々の関心という希少な商品
反対意見ボタンとセレンディピティボタン
ほか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Mc6ρ助
ただの人間
ざっきい
marukuso
がっちゃんギツネ
-
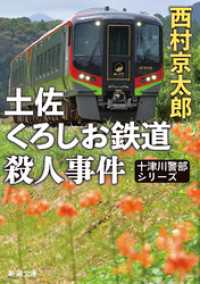
- 電子書籍
- 土佐くろしお鉄道殺人事件(新潮文庫) …
-

- 電子書籍
- 25ans 2016年2月号