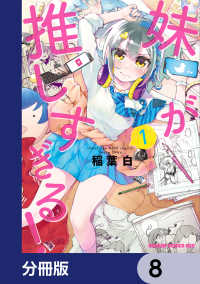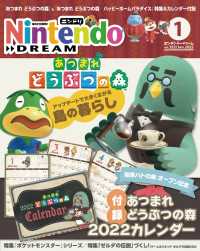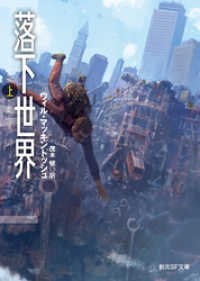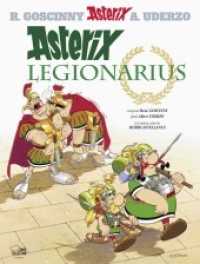内容説明
地域の文化施設を活用したコミュニティづくりの先進事例
今、美術館などの地域の文化施設がハブとなり、人をつなぐコミュニティづくりを行う地域連携プロジェクトへの注目が高まっている。
その潮流の牽引役である東京都美術館と東京藝術大学がタッグを組み、美術館を拠点にアートを介してコミュニティを育む「とびらプロジェクト」の全貌をまとめた一冊。
※一部カラーが含まれます。
コラム:
西村佳哲(働き方研究家 リビングワールド代表/とびらプロジェクト・アドバイザー)、
日比野克彦(東京藝術大学美術学部教授)、森司(アーツカウンシル東京 事業推進室 事業調整課長/とびらプロジェクト・アドバイザー)
○とびらプロジェクトとは?○
東京都美術館×東京藝術大学 とびらプロジェクト
美術館を拠点にアートを介してコミュニティを育むソーシャルデザインプロジェクト。
広く一般から集まったアート・コミュニケータ「とびラー」と、学芸員や大学の教員、そして第一線で活躍中の専門家がともに美術館を拠点に、
そこにある文化資源を活かしながら、人と作品、人と人、人と場所をつなぐ活動を展開している。
東京都美術館のリニューアルオープンをきっかけに、東京藝術大学と連携し2012年に始動した。
「とびラー」とは、東京都美術館の略称「都美(とび)」と、「新しい扉(とびら)を開く」の意味が含まれた愛称。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
zoe
22
東京都美術館+東京芸術大学+40人の市民(1年あたり)で、3年任期で取り組む「とびらプロジェクト」。無償だけれどボランティアではなく多種多様なメンバーが集まり、アート・コミュニケーターとして活動する。美術や音楽には、例え戦時中でも、自然と人を集めて、人間らしさを確認させる力があり、ミュージアムはそんな人間社会の重要な装置である。コミュニケーターによって受けた刺激は、子供たちが大人になったのち、きっと次世代へと恩送りされるに違いない。この指とまれ。そこにいる人が全て式。対等。ミュージアム・スタート・パック。2018/12/02
Yuko
7
数年前に「ヨリミチビジュツカン」に参加したのがきっかけでこの活動を知った。その時の缶バッジはまだバッグにつけて大切にしている。「真珠の耳飾りの少女プロジェクト」でも長女がターバンを巻いて写真を撮ったのが懐かしく思い起こされ、昨年は藤田嗣治の額縁プロジェクトにも参加した。「プーシキン美術館展」マインドマップで味わうアートも楽しかったな。赤ちゃん連れOKの「ベビーカーツアー」や、”Knock-Knock”の活動も素晴らしい。様々な地域への広がりも見えて、これからがますます楽しみな活動。 2019/01/06
雑食読み
4
自分でとびらーに入っときながら今更読む。自分たちがやってる活動ってこういうことか!と改めてわかった。新しいプロジェクトなんだな!2019/03/21
りんご1つ
3
この指とまれ方式、きく力、そこにいる人がすべて方式 、初めに決める終わり方…今まで属したどんな組織でも出会ったことのないやり方で、終始わくわく読み進めた。 『アートコミュニケータとしての活動に、マニュアルはない。その場、その時、その人に寄り添い、よく考え、行動しなくてはならない。故にとびらーは『サポーターではなく、プレイヤー』なのだ。』指示され動くのではなく、個々人の自主性で活動しているから前向きなエネルギーが沸くのだろう。 ギフト&ギフトの関係で、市民と大学と美術館が共に為すプロジェクト。素敵! 2025/02/25
すわ
2
アートコミュニケーションの本。自分がいまやってるサイエンスコミュニケーションの活動と似ているところや独自のところがあって興味深かった。とびラーの応募者の多さにびっくり。芸術と一般市民をつなげる活動は、世の中が豊かになるためにどんどん進めていくべきだと思う。面白かった!2023/01/27