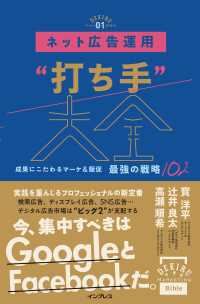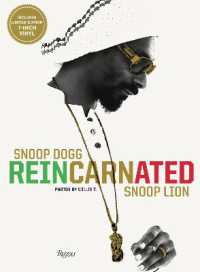- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
卑弥呼、推古、持統……、古代の女性統治者/女帝はどのような存在だったのか。かつては「中つぎ」に過ぎないと考えられていたが、この四半世紀に研究が大きく進み、皇位継承は女系と男系の双方を含む「双系」的なものだったことがわかった。七世紀まで、天皇には女系の要素も組み込まれていたのだ。古代王権史の流れを一望し、日本人の女帝像、ひいては男系の万世一系という天皇像を完全に書き換える、第一人者による決定版。
目次
序章 古代双系社会の中で女帝を考える
女帝は例外か普遍か
双系社会と長老原理
見のがされてきた史実
Ⅰ 選ばれる王たち
第一章 卑弥呼から倭五王へ
1 卑弥呼と男女首長
卑弥呼「共立」
「会同」に集う男女
卑弥呼の墓とヤマト王権
〝一夫多妻〟と男女の首長
2 倭五王と将軍号
倭五王の系譜関係
冊封記事の「世子」
「倭」姓の意味
将軍号と府官
甲冑を副葬する男性首長
3 伝承のイヒトヨ
飯豊王の執政
鳥獣名の男女首長
伏流する女性首長
卑弥呼とワカタケル
第二章 世襲王権の成立
1 婚姻と血統の重視
継体の即位
欽明とその子たち
濃密な近親婚の意味
2 世代原理と即位年齢
熟年男女の即位
長老の統率する社会
群臣が〝えらぶ〟王
3 キサキと大兄
大王とキサキの別居慣行
「娶いて生む子」の系譜
男女の「王」
同母子単位の「大兄」とキサキ
Ⅱ 王権の自律化をめざして
第三章 推古──王族長老女性の即位
1 群臣の推戴を受けて
異母兄敏達との婚姻
継承争いを主導
崇峻の失政から額田部即位へ
欽明孫世代の御子たち
子女婚姻策の狙いと挫折
2 仏法興隆と遣隋使派遣
「三宝興隆」詔と馬子・厩戸
讃え名「カシキヤヒメ」
『隋書』にみる倭国の王権構造
小墾田宮の外交儀礼
3 蘇我系王統のゆくえ
「檜隈大陵」への堅塩改葬
「檜隈大陵」と「檜隈陵」
厩戸の死と二つのモニュメント
遺詔をめぐる群臣会議
二つの推古陵の意味
第四章 皇極=斉明──「皇祖」観の形成
1 初の譲位
遣唐使派遣と百済大宮・大寺造営
皇極の即位と上宮王家滅亡
乙巳の変と同母弟軽への譲位
姉弟の〝共治〟から破綻へ
2 飛鳥の儀礼空間
重層する飛鳥宮
儀礼空間の創造
母斉明の追福と継承
世代内継承からの転換
3 双系的な「皇祖」観
八角墳の始まり
「皇祖」観の形成
「先皇」斉明の位置
第五章 持統──律令国家の君主へ
1 「皇后」の成立
氏組織の再編
吉野盟約と御子の序列
草壁立太子への疑問
野「皇后」と草壁「皇太子」
「天皇」号と「皇后」「皇太子」「皇子」
2 即位儀の転換
天武の死と持統称制
即位儀の画期性
藤原京の造営
3 譲位制の確立と太上天皇
吉野行幸と高市の処遇
高市の死と軽への譲位
太上天皇の〝共治〟
大宝令制定と遣唐使再開
不比等の登場と役割
付 古代東アジアの女性統治者
新羅の善徳王・真徳王
則天皇帝の統治と評価
女主忌避言説の増幅
Ⅲ 父系社会への傾斜
第六章 元明・元正──天皇と太上天皇の〝共治〟
1 「太上天皇」「女帝の子」「皇太妃」
譲位と即位宣命
「太上天皇」の身位と権能
大宝令の「女帝の子」規定
「皇太妃」阿閇と草壁称揚
2 元明による文武・元正の後見
皇太妃の後見
血統的継承観の浮上
元正への譲位
元明・元正と橘三千代
3 聖武と元正太上天皇
聖武即位と長屋王の変
〝共治〟のはらむ拮抗と緊張
太上天皇の居処
第七章 孝謙=称徳──古代最後の女帝
1 女性皇太子の即位
皇太子制の成立と展開
女性の「皇太子」
太上天皇・皇太后・天皇
2 聖武遺詔の重み
廃太子から大炊立太子へ
群臣による他王擁立の企て
淳仁即位から廃帝まで
3 道鏡擁立構想とその破綻
重祚と皇太子不在
「法王」道鏡との共同統治
熟年男性官人の即位
皇緒観念の確立
終章 国母と摂関の時代へ向けて
後宮の成立と皇后・キサキの変容
太上天皇制の再編
母后と摂政
王権中枢における女性の位相の変化
あとがき
引用参考文献
図表一覧
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
南北
nagoyan
さとうしん
(k・o・n)b