内容説明
学問は即効薬ではない。即効薬ではないが、それなくして即効薬はつくれない。
学問が役に立つとはどういうことか。学者のあり方とは。研究のおもしろさとは何か。元国語科教科書調査官の著者がつづったエッセイ集。「第1部 むなしい学問なのか」「第2部 文学青年から文学研究者へ」「第3部 国文学ひとりごと」でつたえる、学問のススメ。
【学問には、その成果が見えるようになるまでに長い時間を要する分野がある。そのような長い時間がたつと、成果が見えるようになっても、社会と学問との接点はどうしても見えづらい。当の研究者でさえ、往々にしてその接点を捜しあぐねている。しかし、繰り返して言うが、学問は即効薬ではない。即効薬ではないが、それなくして即効薬はつくれない。
成果結果のあらわれるまでに長い時間を要し、社会との接点が理解されにくい学問、それが「虚学」であり、文学部はその「虚学」の巣窟である。】...本書「虚学の論理」より
目次
まえがき
第1部 むなしい学問なのか
虚学の論理
文学部の光景/滅びるか、インド哲学/不変の社会的評価/約束されない「虚学」の未来/学問は即効薬ではない/本当に虚しい学問か/蓄積こそが学問である/開かれた大学とは何か/それから二十年以上を経て
ノーベル賞と旧石器
だれも気づかない共通点/文系・理系を問わない問題/専門家の悲痛な声/学者でない人間に学者の良心を責めてどうするんだ/石器捏造と基礎学軽視、どっちの罪が重い?/雨後の筍が日本を救うか/それから二十年
「勇気をもて。学者の良心を忘れたのか」
霧の撤収作戦/「学者の言うことを信じよう」/武人の激励/「学者の良心を忘れたのか」
共和国は学者を必要としていない
レーニンを永久保存した男/ロシア革命の場合/フランス革命の場合/文化大革命の場合/そして、日本の大学改革の場合
人文学のプリンシプルを忘れるな
研究者は強迫観念を持て/論文集出版の意味/新書本では業績にならないか/グロータース神父の挑発/人文学の戦略/人文学には人文学のフォーマットがあるはず
大学図書館は本を貸し出すな
図書館は貸本屋ではない/貸出件数という亡霊/手をのばせばそこに本がある/地方国立大学の附属図書館をめぐる惨状/先人の遺産が泣いている/いまこそハコモノ行政の出番/知のリージョナルセンターが聞いてあきれる/学生サービスを放棄した大学
第2部 文学青年から文学研究者へ
文学部への道
大学は解体されなかった/国立二期校の風景/文学・歴史のほうに進め/見えなかった文学部という選択肢/遅すぎる反抗期
文芸部部室と無邪気な夢
バスから見た六本松キャンパス/文芸部入部/ファントム墜落と政治の季節/小説の季節のなかで/季節の移ろい/作家への憧れ/停止した時間/「春が来て夏が来て秋が来て」/慌ただしい六本松との別れ/「カインとアベルの息子たち」/だれもいない文芸部部室/彷徨のなかで/文学青年との訣別/跋
中野三敏先生と和本修業
和本との邂逅/靴下の片一方を捜して/おさらば文学青年
今井源衛先生と『学海日録』刊行始末
学海遺著・旧蔵書の行方/妾宅日記の発見/本宅日記とその研究会/文学史登場以前の依田学海/附 新潮文庫収録にあたって
非の打ち所のない先行研究の功罪
厳密な分類の索引は必要か/学際の境界は厳密であるべし/蔵書目録は大雑把であれ/「帝国図書館蔵書目録」の使い勝手/『新編帝国図書館和古書目録』余談/大雑把な先行研究に導かれて/「先行研究」にまつわる誤解
第3部 国文学ひとりごと
作者は本当のことを書かない
国語教科書の注釈/当たり前の事実に注釈は必要か/作者は?をつかないという幻想/韃靼海峡を渡ったてふてふ
二人のタケウチ氏をめぐる因縁譚
四国の厳しい一読者/二人のタケウチ氏/奇しき縁
資料を読み解く面白さ
江戸藩邸とは/歴史資料としての手紙と日記/日記はことの詳細を記述しない/印旛沼開発一件の駆け引き/維新後に伏せられた事実/戊辰戦争と佐倉藩の一挿話/新たな発見をして
語る〈時間〉、語られる〈時間〉
ほか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さとまる
明るいくよくよ人
me23
まっつー
Ksbutm
-

- 電子書籍
- 入れ替わった契約婚の花婿は砂漠の王子【…
-

- 電子書籍
- 羅刹の家 第一部 愛蔵版 4
-

- 電子書籍
- サムシングフォーブルー~わたしのしあわ…
-
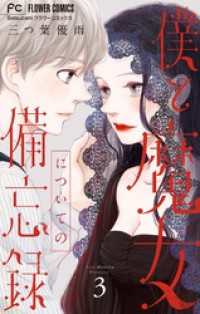
- 電子書籍
- 僕と魔女についての備忘録【デジタル限定…
-
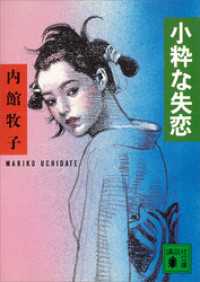
- 電子書籍
- 小粋な失恋 講談社文庫




