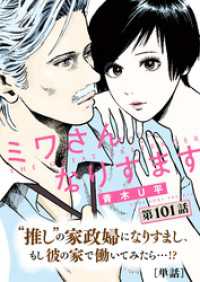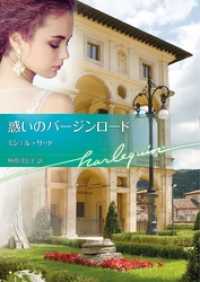内容説明
アダム・スミスの「神の見えざる手」からディズニー映画「アナと雪の女王」まで、人間の歴史を「手を使って行うことの変化」として読み直す。文化や歴史、心理学や精神分析の理論を横断しながら、自分自身や他者との関係、現代に潜む病理を、ユーモアを交えつつ鋭く描き出していく。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おっとー
5
手にまつわるエトセトラ。独裁者の繊細な手仕事、スマホを触ること、成長の過程で口から手へと比重が移ること。普段何気なく使用している手・触覚についてのもろもろをエッセイ形式で気ままに綴っていく。精神分析を専門としているせいか、少し強引な結び付け(iPhoneの「i」の意味やアラジンがランプを擦ることの意味など)が見られるのと、個々のエピソードについてもう少し考察を深めてほしいなーというのとが残念なところ。しかし、五感の中でも一番中動的である手の不思議さを考えるには、面白いヒントがたくさん詰まっている。2022/07/30
たろーたん
4
「手は他者から触れられ、支配される受動的な器官でありながら、その同じ手が他者の支配から自らを引き離し、自由を可能にする能動的な器官でもある」という逆説。一方では「手遊び」の禁止など手をめぐる様々な儀礼が強要され、手はとりわけ私たちの身体が他者によって支配される際の焦点となる場所である。しかし、私たちはその支配の隙間を縫うように、自傷や自慰など自分の身体を触ったり引っ掻いたりする。こういう点から手について考えるのは面白いと思った。2022/06/12
yo_c1973111
1
モノとしてスマートフォン、食べ物、タバコ、ハンカチ、手袋(!)などが時代の象徴や生活中のアイテムとして挙がられ、それらは手をもちいて扱われるから、手の行為は人間の重要な何かを示すと(??)。健常者において手を使わない生活はありえず、人の営みとしての歴史は当然手が介在している。つまり本書の殆ど(第2章除く)には、何も書かれていないと同義だ。また著者の言う「人間」とはキリスト教徒の西洋人のみを指し、その他は人間の範疇にはらないと思われる。2200円(+税)によって得られたものは紙とそこに刷られたインクだ。2021/04/11
ルンブマ
1
「手は他者から触れられ、支配される受動的な器官でありながら、その同じ手が他者の支配から自らを引き離し、自由を可能にする能動的な器官でもある。」なるほど、ラカン派で語られてきたデリダの「蚕」を参照した創造論の具体例として「手」を持ってきたのか。2020/11/10
kentake
0
本書では、人間の手が持つ不思議な機能について、精神分析家としての視点から記述されている。人間は自分の意識の対象を通常は眼の動きで示すが、眼の機能が未発達の生後まもない幼児は、意識の対象を手の動きによって伝えるという。大人になっても、手にはそのような精神的な機能が隠されており、その動きは人間の精神と大きく関連する。クリミア戦争では、帰還兵の神経を落ち着かせるために編み物や刺繍が奨励されたという事例が紹介されているが、感覚的に良くわかるような気がする。2021/04/23