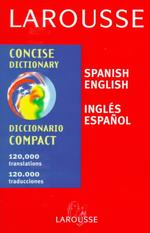内容説明
英語の達人をめざすなら,類義語との違い,構文や文脈,共起語などの知識に支えられた高い語彙力が不可欠だ.記憶や学習のしくみを考えれば,多読や多聴は語彙力向上には向かない.語彙全体をシステムとして考え,日本語と英語の違いを自分で探究するのが合理的な勉強法なのだ.オンラインのコーパスや辞書を利用する実践的方法を紹介.
目次
はじめに┴第1章 認知のしくみから学習法を見直そう┴第2章 「知っている」と「使える」は別┴第3章 氷山の水面下の知識┴第4章 日本語と英語のスキーマのズレ┴第5章 コーパスによる英語スキーマ探索法 基本篇┴第6章 コーパスによる英語スキーマ探索法 上級篇┴第7章 多聴では伸びないリスニングの力┴第8章 語彙を育てる熟読・熟見法┴第9章 スピーキングとライティングの力をつける┴[ちょっと寄り道] フィンランド人が英語に堪能な理由┴第10章 大人になってからでも遅すぎない┴探究実践篇┴本書で紹介したオンラインツール┴参考文献┴あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
旅するランナー
228
認知科学の概念「スキーマ」(言語を使うときに必要となるほとんどの知識は、知っていることが意識されない暗黙の知識)を通して、効率的で確実な語学学習の進め方を示す。Weblio英和・和英辞典、SkELL、COCAなどオンラインツールを活用して、体で覚えるくらいまで落とし込む必要があります。それと、映画を「熟見」する学習法も紹介されています(ここでは007シリーズ「スペクター」)。隙間時間にチョコチョコ学習しているだけでは、なかなかここまで語学力を高められそうにありません。でも、めげずに地道にやっていきます。2021/06/13
KAZOO
138
私はこのような分野の本を何冊か読んできて、そのたびにいつもがっかりしてきたことを思い出しました。この本はそれまでの本とは異なりかなり理論的に現在の脳科学の観点からの成果を取り入れて納得できるような気がしました。只やはり思うのはそれだけの根気と時間をつくりだしていかねばならないということで果たして自分がどこまでやれるのかは自信がありません。2021/01/12
kk
110
認知科学の見地から、「暗記しないで英語をマスター」だの「1週間で英語ペラペラ」だのといったイージーな英語学習法をバッサリ切り捨て、地道にじっくり勉強していくことの大切さを強調。特に、外国語を習得していく上での「スキーマ」の重要性に着目し、コーパス等を活用しながら語彙と語感を涵養していくことこそが、ちゃんとした英語を使いこなせるようになるための王道であると主張。著者の提唱するとおりに実践するのは時間的・労力的にかなりたいへんですが、仰ることはイチイチご尤も。折に触れてときどき思い出したい視点だと思いました。2021/05/01
アキ
97
日本語で捉えている世界を英語はまた違うシステムで見ている。英語を学ぶのに最も重要なのは、氷山の水面下にある言語化できない「スキーマ」であり、多読だけでは得られないものである。SKELLというコーパスにより学ぶことを具体的に示す。例えば英語の名詞のentityの基礎は、objectかsubstanceが生き物か否かより枝分かれの上位にあるため可算・不可算が重要になる。映画「007スペクター」の熟見や、大人なってからの長期的な間隔学習、フィンランド人が英語に堪能な理由など垣内晴氏のイラストともに楽しめました。2021/05/13
k sato
86
認知科学に基づく合理的英語学習の教本。上級者向け。思い込み学習に警告する著者。多読や多聴をしても「スキーマ」がなければ英語は熟達しない。スキーマとは、母語の知識体系のことで、無意識下に存在する知識のネットワークだ。学習者は、英語と日本語のスキーマが全く異なることを認識しなければいけない。例えば、単語が使用される文脈、共起する単語、単語の多義などの骨組みの違い。高難度の単語を学ぶ必要はなく、平易な単語を深耕することでよい。これが、筆者がいう語彙力だ。赤ちゃんが母語を習得する過程も説明されており説得力がある。2023/02/01
-
![[ハレム]あなたが甘くねだるまで 第27話 ハレム](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1166702.jpg)
- 電子書籍
- [ハレム]あなたが甘くねだるまで 第2…