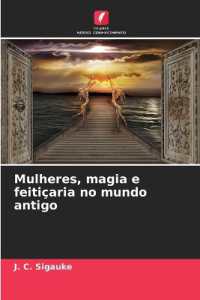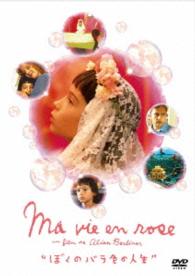内容説明
台地と低地、海と湿地と川がおりなすダイナミックな地形を活かして作られた「坂と水の町」東京。徳川幕府による計画、大火や地震などの災害、文明開化、戦争、高度成長など、現在の発展の前には、都市が劇的に変革する数多の大きな起点が存在していました。それらのプロセスや出来事の重要性を、古地図・史料・風景写真、そして現代のまちを歩いて得た知見などを交えつつ、「ブラタモリ」にも出演した都市形成史の専門家がわかりやすく解説します。オリンピックを控える今、江戸の町と現在の町の利点・難点を比較し、未来の町づくりを考えるきっかけとなる一冊です