内容説明
環境を扱う学術研究はあらゆる領域において活発であり、それらを統合する分野としての環境学も確立されつつある。しかし個々の領域の閉鎖性は根強く、さらに行政と市民団体など、環境問題に取り組む主体間の連携も希薄である。本書はこのような課題の克服を目指し、同時に、組織としての環境問題への取り組みの変遷・展望を紹介する。
目次
序章 環境問題の背景から政策の糸口を探る
第I部 各学術分野における環境研究の動向と展開
第1章 環境法の歴史的変遷[金光寛之]
1.1 戦前の環境問題
1.2 高度経済成長期の公害問題
1.3 公害・環境問題の多様化
1.4 環境法の新展開
第2章 わが国における環境研究の動向と展開[熊澤利和]
2.1 はじめに
2.2 掲載論文等数の推移
2.3 論題に「環境汚染」を含む論文等の分析
2.4 1950~1969 年の論題分析
2.5 1970~1989 年の論題分析
2.6 1990~1999 年の論題分析
2.7 2000~2004 年の論題分析
2.8 2005~2009 年の論題分析
2.9 2010~2014 年の論題分析
2.10 論題に「行政」を含む論文等からの分析
2.11 考察
2.12 おわりに
第3章PM2.5 問題をめぐる環境政策の軌跡と新展開[飯島明宏]
3.1 序論――メディアに扇動されたPM2.5問題
3.2 PM2.5 問題に対する環境政策の歩み
3.3 PM2.5 騒動以降の政策展開
3.4 結論
第4章 社会基盤政策と環境政策[伊藤豊・馬奈木俊介]
4.1 はじめに
4.2 環境影響評価
4.3 公共事業評価としての費用便益分析
4.4 環境評価手法
4.5 まとめ
第5章 再生可能エネルギー普及のための政策[山本芳弘]
5.1 はじめに
5.2 汚染物質排出削減のための政策
5.3 再生可能エネルギーの普及策
5.4 FIT のバリエーション
5.5 今後のFIT のあり方
5.6 再生可能エネルギー利用と省エネルギー
5.7 おわりに
第6章 家計への環境政策:行動心理を考慮した新政策[岩田和之]
6.1 はじめに
6.2 従来の環境政策
6.3 家計に対する環境政策の問題点とナッジを用いた環境政策
6.4 まとめ
第7章 環境問題をマーケティングの視点で捉える:CSV(共通価値)の形成[佐々木茂]
7.1 はじめに
7.2 マーケティングにおける環境問題の捉え方の変遷
7.3 環境対策による地域イメージの改善と観光産業への発展によるさらなる進化
7.4 環境マーケティングの普及促進に向けて
第8章 環境会計と情報開示の新展開:資本概念の拡張[水口剛]
8.1 序論
8.2 レビュー
8.3 分析および考察
8.4 結論
第9章 地理教育における環境問題の取扱いと温暖化の実態[大島登志彦]
9.1 はじめに
9.2 地理教育における環境問題の取扱いの変遷と課題
9.3 温暖化の進捗
9.4 環境問題や温暖化から派生する現象
9.5 おわりに
第10章 環境教育の成果と課題[片亀光]
10.1 環境教育の目的と現状
10.2 環境教育の成果
10.3 環境教育の今日的課題
10.4 環境教育を発展させるために
第II 部各政策セクターにおける環境政策の動向と展開
第11章 2020年目標に向けた温暖化政策のあり方について[堤達平]
11.1 テーマの背景および論文の目的
11.2 これまでの温暖化施策について
11.3 これまでの温暖化施策の評価・課題について
11.4 事業者の温暖化対策を効果的に促進するための方法について
11.5 考察
第12章 環境リスク時代の環境政策[田子博]
12.1 はじめに
12.2 環境問題と世間の認識
12.3 リスクコミュニケーションとリテラシーの向上を目指した環境教育
12.4 おわりに
第13章 東アジアにおける大気環境管理に関する国際的取り組みの現況と将来課題[佐藤啓市]
13.1 はじめに
ほか
-

- 電子書籍
- 魔鬼【タテヨミ】第81話 恋々バニラ
-

- 電子書籍
- 異世界建国記(9) 角川コミックス・エ…
-

- 電子書籍
- テスラノート(5)
-
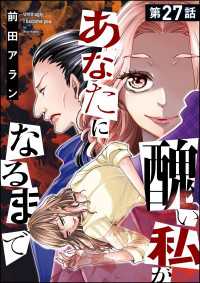
- 電子書籍
- 醜い私があなたになるまで(分冊版) 【…
-
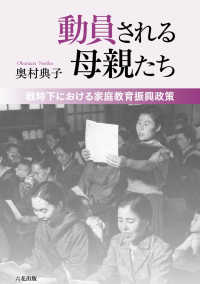
- 電子書籍
- 動員される母親たち - 戦時下における…



