内容説明
西欧倫理思想に最も大きな影響を与えてきた古典でありながら、プラトンの『ソクラテスの弁明』などにくらべてわかりにくい印象のあった『ニコマコス倫理学』。本書はその全10巻を、テキストの文章をできるだけ具体的に引きながら丁寧に解説し、アリストテレスが徳の習得と幸福の関係をどのように捉えていたかを明らかにする。
目次
まえがき
序章 アリストテレスと先行思想――ノモスとピュシス
1 「ノモス(法、慣習、規範)」と「ピュシス(自然本来にあるもの)
2 ソクラテスの「徳の探求」からアリストテレスの「徳の教育」へ
3 アリストテレスの存在論とイデア論批判
第一章 幸福(エウダイモニア)とは何か
1 最高善としてのエウダイモニア――「善」と「幸福」を結合する思想
2 アリストテレスの「幸福」観
3 「幸福」についての基本的見解(1)――「幸福」の形式的規定
4 「幸福」についての基本的見解(2)――「人間に固有の機能(エルゴン)」とは何か
5 「幸福」の諸条件
第二章 人はどのようにして徳ある人へと成長するか
1 「徳の教育」の前提である「しつけ、訓練」――「正しい感受性」の育成
2 「快楽、よろこび(hedus)」と「美しさ、立派さ(kalon)」――「美しさ」を認めた行為を遂行することの「よろこび」
3 「性格の徳」の定義のこころみ――中庸説について
第三章 性格の徳と思慮との関係
1 「思慮の働き」と「実践的推論」
2 第二の自然としての、性格の徳と思慮
第四章 徳とアクラシア
1 「アクラシア(無抑制)」はどうして成立するか
2 徳ある人(思慮ある人)と抑制ある人・無抑制な人との区別
第五章 友愛について
1 友愛の三つの種類
2 自己愛と友愛
3 幸福と友愛
第六章 観想と実践
1 観想活動とは何か
2 エルゴン・アーギュメント――「実践的な徳」と「観想的な徳」の解明
3 「観想活動の生」と「実践活動の生」の関係
注
あとがき
『ニコマコス倫理学』出典索引
事項索引
人名索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
buuupuuu
東雲そら
くま
be-
-
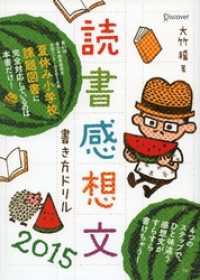
- 電子書籍
- 読書感想文書き方ドリル2015
-

- 電子書籍
- 彼女のカレラEV (6) リイドカフェ…





