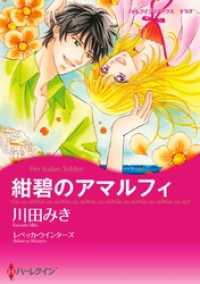内容説明
葦や茅の根の周辺では、鉄バクテリアの作用により褐鉄鉱の団塊が作られることがある。俗に「高師小僧」と呼ばれるこの団塊から、鉄を製錬する技術が弥生時代に存在した―。腐食しやすいために考古学的資料として姿を現さないその褐鉄鉱の痕跡を、著者は神話や祭祀のなかに見出していく。諏訪大社の御柱祭で曳行される柱は製鉄炉の押立柱に由来し、またイザナギ・イザナミの二神こそ古代の鉄文化(鐸=サナギ)を象徴する神であるという。大胆な推論により古代日本の謎に迫る名著、待望の復刊。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ymazda1
5
前半は、低い温度でも製鉄は可能だがら日本の鉄器時代は、もっともっと遡れるけど、粗悪な鉄だったので現代まで痕跡が残っていないみたいな、欧米の超古代文明論っぽい内容・・・鉄の良否は温度云々ではなく、脱炭に代表される鋼としての元素組成のコントロールの問題だと思ったりしたのだけれど・・・そして、後半は、その裏付けとしての地名や人物名の語呂合せ・・・自然科学チック&人文科学チックな視点が織り交ぜられてはいるものの、どちらも、考えられる異論への反証が完全放置されているせいか、なんか、トンデモっぽい印象の本だった。。。
筑紫の國造
4
かなり面白かった。「祭祀学」の立場から各地の寺社の祭祀や縁起の中に「製鉄」につながる要素を探り出し、日本の古代文化に鉄が果たした重要な役割を解き明かしていく。これは文献史学や考古学ではなかなか解明できない部分だろう。著者は自然科学の力も借りながら、しっかり各地の神社や山野をフィールドワークし、自説の補強を展開してゆく。読んでいて、新しい視点が得られたと思う説得力がある。ただし、「鉄」の要素を重要視するあまり、やや自説に強引に附会している部分も見受けられる。考古学、古代史の成果と合わせて考えたい。2022/11/27
ももいろ☆モンゴリラン
3
神話に出てくるあの人もこの人も、あの場所もこの地名も全部「鉄」に纏わるものだった!? 巷間には有名な説なのかもしれませんが、神話と製鉄を絡めた視点が私にはすごく新鮮でした。そして思い出したように放映される金曜ロードショー「もののけ姫」。あれこそ古代の鉄と神々のお話ですよね。腐食してしまう鉄だからこそ物的証拠は残さなかったが、われらが子孫は鉄を名に負い、地に残し、尊いものとしていたんだねえ 本と読みながら「へええ」しか言ってない2018/11/10
io
1
すごくおもしろかった!鉄に由来する言葉・地名・名前が山ほど載ってて、へーへー言いながら読んだ。すずが成ってるの見てみたい。証拠が残らないというのが惜しい…。2019/02/09
甲斐祐貴
1
日本の神社祭祀は製鉄に関わる人々の信仰と密接に関わっているのだと考察されている。 イザナギ、イザナミと銅鐸との関わりなど、とても興味深かった。2018/09/05