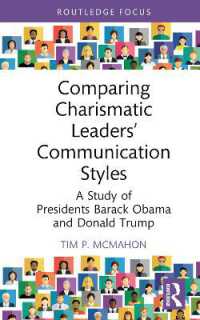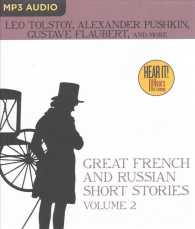内容説明
「ことば」は、いつも身近にあって、なくてはならないものですが、実はとても捉えがたく奥深い現象です。本書では、中学・高校までに学んだ知識を活用し、日本語と英語を比較しながら、「認知言語学」という言語学の一分野を紹介します。
例えば、brotherという英語は、日本語では「兄」か「弟」に区別しますが、この違いは認知言語学ではどのように説明されるでしょうか。ものごとの捉え方(=認知)と言語の仕組みとの密接な関係を解明します
※本電子書籍は画面の大きい端末でお読みいただくのに適しています。
※本電子書籍は文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
目次
序章 言語学
第1章 認知
第2章 認知言語学
第3章 カテゴリー化
第4章 プロトタイプ
第5章 家族的類似性
第6章 スキーマ
第7章 言語カテゴリー
第8章 他動性と動作主
第9章 構文
第10章 多義性
第11章 メタファー・メトニミー
第12章 オノマトペ
第13章 ことばの変化
第14章 日英対照研究
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひ※ろ
1
★★★☆☆2020/08/29
ノンタス
1
はじめての認知言語学 入門の分かりやすい一冊。 用語を解説してくれながら、日常の例を用いて初級学習者にも丁寧に説明する。 この分野での専門用語が結構あり、馴染みない言葉も覚えるきっかけになった。 日英対照が主だったが、そのほかの言語の例をもっと用いていれば更に豊かになったと思う。2019/01/11
ず〜
1
認知言語学の入門的な内容はもちろん、言語研究をするうえでの心構えも勉強になった。この本の著者が言っているように、自分が感じたことばに対する違和感を出発点に研究に取り組めば、独自の視点で深い研究ができるし、何よりおもしろい。ただ、メタファーの説明でよくわからないところがあったのでもう一度読みたい。2017/09/07
ブックりくまさん
1
1~11章までは認知言語学の入門書だったらほぼ必ず触れる内容。12~14章のオノマトペ、ことばの変化、日英対照研究は少し著者の専門にも関わるほんの少し応用編。後半が面白かった。2015/04/27
kozawa
1
入門書としてはあり…かな。2013/03/09