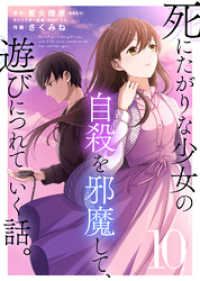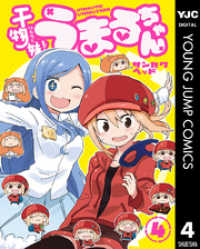内容説明
哲学は、「根源的真理」を問うものではない。その最大の目的は、一人ひとりの生き方と社会のあり方をよりよくすることであり、その方法は、プラトンが描くソクラテスにはじまり、フッサールの現象学にて真価を発揮した「対話」である。そうしてお互いが納得しうる「共通了解」をつくりだす哲学の営みは、分断が極まった現代において、人びとをつなぐ大きな可能性を秘めている。渾身の力を込めて、いま哲学の課題、目的、方法を問いなおす。
目次
はじめに──哲学と共通了解
凡例/第一部 「魂の世話」としての哲学──ソクラテスとプラトン
序 対話の文化
第1章 哲学はどうやって生まれたか──哲学と〈軸の時代〉
第2章 ソクラテスの生きた時代
第3章 魂の世話──『ソクラテスの弁明』
第4章 「~とは何か」の問い──『ラケス』
第5章 哲学対話の可能性
第6章 魂・国家・哲学・イデア──中期プラトンの思想
第二部 「合理的な共通了解」をつくりだす──フッサール現象学の方法
序 共通了解に向かって
第7章 二〇世紀哲学による「本質・真理」の否定
第8章 ギリシア哲学・幾何学・自然科学──共通了解をめぐる問題(一)
第9章 近代科学とともに生まれた難問──共通了解をめぐる問題(二)
第10章 現象学的還元と本質観取──現象学の方法(一)
第11章 現象学と〈反省的エヴィデンス〉──現象学の方法(二)
第12章 〈超越論的還元〉と認識問題の解決──現象学の方法(三)
第三部 どのように哲学対話を実践するか──正義の本質観取を例として
序 正義の本質を探究する
第13章 正義の本質観取──現象学の実践(一)
第14章 正義をめぐる問題と学説の検討──現象学の実践(二)
おわりに──哲学の課題・目的・方法
あとがき
註
資料
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りょ
りょ
ほし
フリウリ
ATS