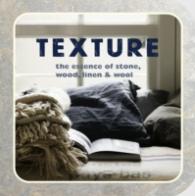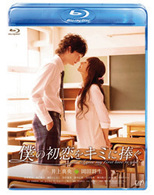内容説明
教育改革をその前提から問い直し、神話を解体してきた論客が、コロナ後の教育像を緊急提言。オックスフォード大学で十年余り教鞭を執った今だからこそ、伝えたいこと。
そもそも二〇二〇年度は新指導要領、GIGAスクール構想、新大学共通テストなど、教育の一大転機だった。そこにコロナ禍が直撃し、オンライン化が加速している。だが、文部科学省や経済産業省の構想は、格差や「知」の面から数々の問題をはらむという。
以前にも増して地に足を着けた論議が必要な時代に、今後の教育を再構築するための処方箋をお届けする。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
TAK.I
12
日本が抱える教育の問題点を鋭く指摘している。日本は事実から帰納的に政策を考えた痕跡がないとはまさにその通りで、日本の決定的に弱い部分と言える。筆者は日本の教育改革を印象論・エセ演繹型思考と論じる。第四部の教育クロニクルの章では、東洋経済誌の時論コラムを時系列に並べ、その時々における教育課題に対して論じている。初見だったので、幅広い話題に触れることができた。ただ、現状について述べられてはいるものの日本の教育がどこへ向かうべきなのかといった道標がいまいち示されているとは思えず、学のない自分には少々難しかった。2021/06/27
Nobu A
10
苅谷先生著書節目の10冊目。通常同著者のをこれだけ読むと使い回しも散見し飽きてくるが、それどころか益々魅力を感じる。時には再読必要な晦渋だと感じるものもあるが。相性が良いのかな。慧眼とも言える着眼点、筋の通った構成力、犀利な考察。帰納型英国と演繹型日本の対比で文科省主導で進む教育改革の問題点を明晰に分析。大学とは何ぞやには複数の論考に触れてきたが、著者の定義付け程府に落ちるものはない。「知の生産・再生産する場」を中心に置かないと話がブレる。人文学の在り方や意義等、勉強なった。一点だけ。第四部は不要かな。2021/04/30
nagata
7
幾度となく施行されてきた日本の教育改革は、つねに欠如態である、と看破されていたのが一番頭に残った。ないものねだりの演繹型思考では空疎な議論にしかならず、また提起されたものごとは実現された試しがない。これまで積み重ねてきた事象を1つ1つ丁寧に分析して帰納型思考を働かせること。ただ、データの取り方など丁寧に進めないと実態は浮かび上がってこない。2025/07/13
hr
3
日本の教育は結局理念を先に決めてしまう傾向があることを痛感する。だいたい「教育目標」だの「建学の精神」だのは、子どもや現場よりも前に決められたものだ。決めた目標や精神自体の検証、育った子どもの実際を検証する術を持たないまま、文科省も現場も有識者たちの教育ポエムに振り回され続けている。大変な国だね、、、2021/08/13
マーチャ
3
今までの教育改革は、事実の検証が確かに不充分だった。地域格差を暴露するとか個の学力状況を知らしめるとか言う微視的論拠に踊らされて。でも、これから世界の中である程度の自由と豊かさを持って生活するなら、実態の把握にを帰納的検証に基づき方向性や伸張する用を見つけていかなければ感情論や経済論だけに振り回されてしまう。これからのビッグデータ利用が不可欠な時代に倫理観や人間性といったものを加味しながら世界的視野に立って教育の方向性を見なければならない時代だと痛感した。2021/04/10
-

- 電子書籍
- 卵焼きキッチンラブ~イケメン彼氏とのお…
-

- 電子書籍
- 14歳のエレジー 絶望中学生日記76 …