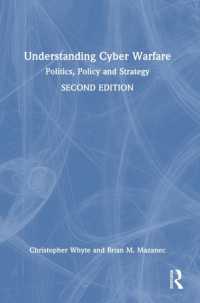内容説明
「無常観を主題とした遁世者の随筆」と言われがちな「徒然草」。でも昔の人だって、簡単に世を捨てられたわけではありません。作者の兼好はどんな社会と人間関係に生きたのか。当時の文脈に置きなおすことで、本当の姿が見えてきます。
目次
はじめに
第一章 かくてもあられけるよ
事実か虚構か
「栗栖野」のイメージ
連想の糸でつながる章段
第二章 時間よ止まれ
「すべてを捨てる」生き方
「空の名残」
それでも心を動かすもの
【コラム】徒然草の本文──烏丸本
本文を定める
たった一字の違いでも……
第三章 歌人としての兼好
和歌四天王
和歌世界の枠組み
実体験の歌、物語を題材にした歌
「恋の歌」の詠み方
なかなかの歌人
第四章 奇蹟が起きたら
大根が勇士となって……
兼好好みの「聞き違い」
奇蹟に対する距離の取り方
第五章 捨ててよいのですか?
最も人気のない箇所
おんぼろ書類ケース
「まかり」の謎
古くて汚いけれど
第六章 太平記の兼好
ラブレターの代筆
教科書としての太平記
権力者との距離
第七章 人の上に立つ人
人材が輩出する北条氏
松下禅尼の警告
エピソードに潜む同時代批判
第八章 自己紹介
役割を意識した自慢
馬術はたしなみ
巻子本時代の情報アクセス能力
当代きっての学者の誤りを指摘
書道の知識
見えない存在
対応を間違えると……
兼好の主人は誰か
第九章 源氏物語から徒然草へ──つれづれなる「浮舟」
宇治十帖への共感
和歌と源氏物語
手習巻を思いながら
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きみたけ
63
著者は慶應義塾大学文学部教授の小川剛生先生。「徒然草」の内容を俯瞰的に分析し、新たな解釈とともに取りまとめた一冊。途中のコラムにも記載していましたが、兼好自筆の徒然草の本文には句読点がなく、後世の学者による区切り方の違いで解釈も変わってくるそうです。正直、高校の古文の授業の時以来で、日常の雑多な話題だけでなく太平記や源氏物語の内容にも触れているとは知りませんでした。きちんと読めば、現代社会にも通じる内容であったことに改めて驚きました。2023/06/30
クロメバル
14
兼好の「遁世」は方便。修行一途などとはとても言えない。兼好は、その教養と歌人としての才により六波羅探題の長官であった金沢貞顕(かねさわさだあき)に仕えていたと考えられる。その視点で読み直すと、通りの良くなる章段がある。ーーこれまでの兼好法師像が覆る。中公新書の『兼好法師ーー徒然草に記されなかった真実』も読みたくなった。2022/01/18
しずかな午後
9
厭世的な隠者の文学という、従来の『徒然草』のイメージから距離を置いて、知力でもって有力者に仕えた秘書官という兼好の実態をもとに『徒然草』を読み直す。もちろん兼好の伝記は、従来思われていたような吉田家出身の隠者ではなく、鎌倉幕府の要人(金沢貞顕)の右筆であったという、小川氏の研究にもとづくもの。兼好の伝記が新しくなったことが、どう『徒然草』の読みに関わるのか、それを明らかにする一冊。読書案内としても優秀、好著。2023/08/12
糸くず
9
教科書的な兼好法師のイメージを刷新した『兼好法師』(中公新書)の著者による徒然草のガイドブックなので、さすがの面白さと読み応え。鎌倉時代末期の権力者たちの間で縦横無尽に活躍する非公認の有能な秘書としての彼を鮮やかによみがえらせ、俗世間に生きる他ない人間の孤独に迫る。「最も人気のない」九九・一〇〇段を取り上げた第5章が素晴らしい。「唐櫃」「土器」「まかり」などの語をひとつひとつ丁寧に読み解くことで、「伝統文化の継承」についての兼好の考えを紐解く。学者が書いた本を読む醍醐味がたっぷり詰まっている。2020/11/28
6haramitsu
5
兼好の実像に迫ってて面白い。 ながーい歴史の中で、江戸時代とかに編纂されたりして、いろいろ物語になったりしてるのね。 それを紐解いていってくれる。 当時の文化なども面白い。頭巾を被って、皇室行事とかを見に来てるとか、やっぱり昔の時代はゆるくていいなぁ。これが本来の日本文化なんじゃないかな。 厳格さとか形式とかごちゃごちゃいじっていって、ブラックボックス化密室化していったのかな。 しかし、兼好はマルチに活躍しててすごいなぁ。隠遁者というよりバリバリのインテリコンサル。金沢北条氏とこんなに縁があったのか。2022/09/10
-
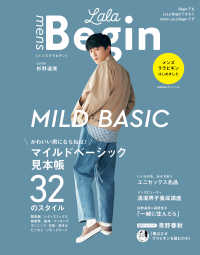
- 電子書籍
- mens LaLa Begin
-
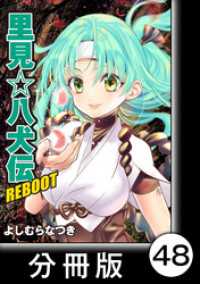
- 電子書籍
- 里見☆八犬伝REBOOT【分冊版】(4…