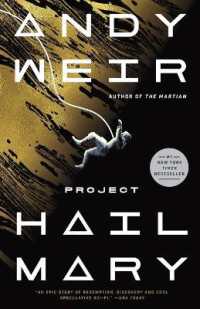内容説明
「生物学」はここから始まった! 現在もアップデートされ続ける進化論の礎を読み解く
たまたま起きる変異が自然淘汰を経て、新たな形質として獲得され種が増えていく。進化とは枝分かれの歴史である。進化の原動力を解き明かしたダーウィンの進化論は現在も概ねその正しさが証明されている。一方、弱肉強食、優生思想といった誤解もつきまとってきた。 いま進化論を読むことの意義とは? ダーウィンの理論からエピジェネティクスなど最新の遺伝学まで、人類史を振り返る意味でも、ホモ・デウス化する人間の未来を見通す意味でも、読解必須の書。
第1章 「種」とは何か?
第2章 進化の原動力を解き明かす
第3章 「不都合な真実」から眼をそらさない
第4章 進化論の「今」と「未来」
特別章 ダーウィン『種の起源』以降の発展
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
76
2015年放送「NHK100分de名著」の番組テキストが底本。著者は総合研究大学院大学学長で進化生物学者の長谷川眞理子氏。本書で取り上げるダーウィンの『種の起源』は大変有名だが読んだことはない。「神様が天地創造の際にすべての生き物をつくり、動物も植物も変化することなく今に至っている」というキリスト教的世界観を根底から覆し、「進化」の科学的世界観を示してくれたのがダーウィンの著書『種の起源』でした。本書では、冗長でまわりくどい感のする古典的名著のエッセンスを、現在からの視点で、わかり易く解説してくれる。⇒2025/02/03
esop
67
生物とは不変のものではなく世代を経て次第に変化していくものである/競争のない場所には進化は起こらない/有利な変異は保存され、不利な変異は排除される過程でー環境に有利な形質は存続しそうでない形質は消える/変異、生存競争、自然淘汰/進化とは決して上を目指す「進歩」などではなく、異なる環境に適したさまざまな生き物を生み出す、枝分かれの歴史です/いかなる種でも変異した子孫は構造を多様化すればするほどうまく生存できる可能性が高くなり、他の生物が占めている場所に侵入できるようになる/地球上の生き物はすべて繋がっている2024/09/23
樋口佳之
46
2015年8月に放送された「NHK100分de名著」の番組テキストを底本として一部を加筆・修正…特別章「『種の起源』が開いた扉」、読書案内などを収載/既に優性劣性は顕性潜性になったけども、「進化論」は「分化論」、「自然淘汰」も「自然選択」一本にになった方が良いと思いました。分野の専門家以外の中では大変な誤解が生じているのだから。/(遺伝子レベルで関係性の薄い)「見ず知らずの人を助ける『利他行動』は、進化の理論では実は説明がつきにくい/意外とたまたまだったりするのかも。2024/02/24
GELC
16
先日読んだジャネット・ブラウンの著者は、種の起源の解説書というよりサイドストーリーだったので、原著に挑む前に本書にも取り組んだ。最近気に入っている雑草学の稲垣先生の著作でよく目にする、ノイズにこそ価値があるということや、全ての生物が進化の最前線に位置しており等しく尊いこと等が語られていて驚いた(解説者の長谷川先生の解釈も入っていそうだが)。とかく我々は人間が進化の頂点で、他の生物より価値があると思いこんでしまうことの浅ましさを痛感させられる。また、エピジェネティクスという概念を初めて知り興味深かった。2024/01/28
Lagavulin
8
生物系の本には生きるヒントが詰まっている。原著を読みたくなった。2021/10/06
-

- 電子書籍
- ただいま、おじゃまされます!(フルカラ…
-
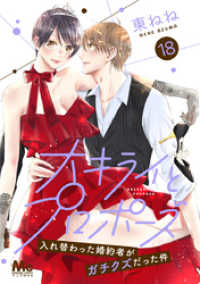
- 電子書籍
- 大キライとプロポーズ~入れ替わった婚約…
-
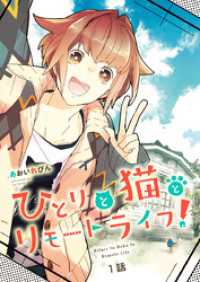
- 電子書籍
- ひとりと猫とリモートライフ!(1) カ…
-

- 電子書籍
- 過去の呼び声【分冊】 4巻 ハーレクイ…