内容説明
福沢諭吉の最高の思想的作品「文明論之概略」を、丸山真男氏とともに読む。この中巻では、第四章から第七章までをあつかい、智徳の社会的な在り方がテーマとなる。丸山氏の講義は、福沢がここで主として活用したバックルの文明史を丹念に参照しながら、歴史と社会の認識論を中心に進められる。政教一致のイデオロギーや徳育中心主義の盲点を明らかにすることを通して、福沢の時代認識と問題意識とが鮮烈に浮かび上がってくる。
目次
第七講 文明史の方法論 第四章「一国人民の智徳を論ず」一┴第八講 歴史を動かすもの 第四章「一国人民の智徳を論ず」二┴第九講 衆論の構造と集議の精神 第五章「前論の続」┴第十講 知的活動と道徳行為とのちがい 第六章「智徳の弁」一┴第十一講 徳育の過信と宗教的狂熱について 第六章「智徳の弁」二┴第十二講 畏怖からの自由 第七章「智徳の行はる可き時代と場所とを論ず」一┴第十三講 どこで規則(ルール)が必要になるか 第七章「智徳の行はる可き時代と場所とを論ず」二
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゃん
15
本書は、『文明論之概略』の第4章「一国人民の智徳を論ず」から第7章「智徳の行はる可き時代と場所とを論ず」までの解説。『文明論之概略』の各章を読んだ後、本書の対応部分を読むようにしている。『文明論之概略』(岩波文庫)の注釈を読んでも分からないところが、本書を読んですっきりすることが多々あり、大変有用。福沢諭吉の当時の時代認識と問題意識を戦後の視点から読むと、また新たな問題意識が生まれるところが本書の面白いところ。下巻へ進む。2017/02/18
かんがく
10
中巻では知徳を論じた4~7章を扱う。道徳論を扱う部分が多く前巻に比べると面白さは劣るものの、引き続き福沢と丸山の凄さを感じた。日本人が話し合いが苦手というのは、明治も昭和も現在も変わらない。2020/04/05
かす
8
主に智と徳について。徳の影響を及ぼす範囲は限られており智の発達により周囲に大きな影響を、との意が自分にささる。社会に影響を与えられる人になってくださいという教授の言葉を思い出す。現代ではSNSで個人の受信・発信力も増し尚のこと智と徳の両方の発達が求められる。衆論と時勢。主張は至極もっともで衆論を発達させる手段が悩ましい。現代で一番影響力があるのはワイドショーでありその内容は視聴者への共感をベースに製作されているように感じられ学べるといえるかは疑問。他方SNSも自分好みの情報が集まりやすい。2020/07/12
あかつや
5
中巻は『概略』の第四章~第七章まで。智とは徳とは、それが社会でどういった意味を持つのかということを扱った部分を解説していく。福沢の偉いのは、何かを論じる前にその論じる所を曖昧なままにせず、しっかりと規定してからはじめることだなあ。そんな福沢の特徴がわかる言葉の使い方とか文章の置き方など、そういう細かい部分もくわしく解説してくれてとても面白い。あと戦前に軍部の検閲で削除された箇所の解説も興味深い。でも当時の軍部の暴走にチクリとやりたいのはわかるが、福沢流に捉えるなら「衆論の非を憂ふ可き」だよなあとも思った。2019/04/08
Tai
4
徳は一身家族まで、定まって動かず、普遍的。智の活動の不断の進歩。影響は全世界に及ぶ。徳を広めるのは聡明叡智、智の力。/人民の間に分賦した智徳の向上が明治維新の遠因である。/生活習慣が可変的なものだ、という前提が大事。福沢は、学問は第一がはなし、次にものごとを見たりきいたり、次には道理を考え、その次に書を読む、としてる。人が集まって合議する習慣をつけたい。/学問とは「物事の互ひに関り合ふ縁を知る」ことだ。/バックル・疑いの心。懐疑なくして探求なく、探求なくして知識はない。/知性の勇気。2020/02/23
-
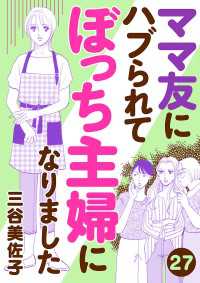
- 電子書籍
- ママ友にハブられてぼっち主婦になりまし…







