- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
(目次)
プロローグ 『日本書紀』一三〇〇年紀に向けて
第一章 中世日本紀の世界へ
1.『釈日本紀』と「日本紀の家」
2.『太平記』が伝える「中世日本紀」
第二章 戦乱のなかの『日本書紀』
1.伊勢神宮に伝わった「秘書」
2.応仁・文明の乱と吉田兼倶
第三章 「日本紀講」と平安貴族たち
1.「日本紀講」の現場へ
2.『源氏物語』のなかの「日本紀」
第四章 儒学者・国学者たちの『日本書紀』
1.山崎闇斎・出口延佳・新井白石――儒学系の学者たちはどう読んだか
2.本居宣長・平田篤胤・鈴木重胤――国学者たちが読む『日本書紀』
第五章 『日本書紀』の近・現代史
1.維新変革のなかの『日本書紀』
2.近代学問は『日本書紀』をどう読んだのか
第六章 天武天皇・舎人親王・太安万侶――『日本書紀』成立の現場へ
1.『古事記』『日本書紀』、ふたつの神話世界
2.「日本紀講」に埋め込まれた神話
あとがき
-

- 電子書籍
- NHK きょうの料理ビギナーズ 202…
-
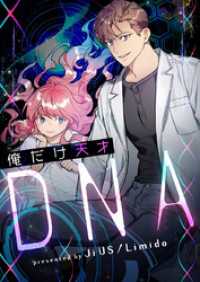
- 電子書籍
- 俺だけ天才DNA【タテヨミ】第26話 …
-

- 電子書籍
- 陰のハンターはSSS級悪魔と契約する …
-
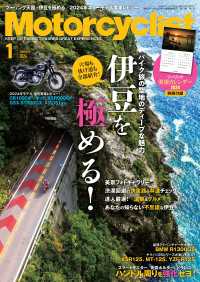
- 電子書籍
- Motorcyclist 2024年 …
-
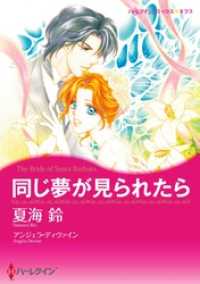
- 電子書籍
- 同じ夢が見られたら【分冊】 5巻 ハー…



