内容説明
主に質問紙調査などによって、哲学の問題に関する人々の直観を明らかにする実験哲学。経験的手法による既存の哲学理論の検証や、哲学的な問題を考える際の心のメカニズムの解明、従来の哲学研究の方法論そのものの問い直しなど、多様な方向性を持つ。認識論、言語哲学など各分野の代表的な研究を紹介し、課題と可能性を展望する。
目次
はしがき[鈴木貴之]
第1章 実験哲学とは何か[鈴木貴之]
1.1 哲学と事例の方法
1.2 事例の方法から実験哲学へ
1.3 実験哲学の広がり
文献案内
第2章 知識の実験哲学[笠木雅史]
2.1 実験哲学の開始とその後の展開
2.2 知識の分析とゲティア問題
2.3 ゲティア型事例についての文化比較研究
2.4 直観的判断の相違によるゲティア型事例の分類
2.5 知識の実験哲学の意義
第3章 言語の実験哲学[和泉 悠]
3.1 はじめに
3.2 「意味論、文化横断的スタイル」という論文
3.3 方法論的批判
3.4 実験内容に関する批判
3.5 おわりに――今後の方向性
第4章 自由意志の実験哲学[太田紘史]
4.1 はじめに
4.2 素朴両立論を支持する研究
4.3 素朴非両立論を支持する研究
4.4 研究の進展と多様化
4.5 哲学的意義
第5章 行為の実験哲学[笠木雅史]
5.1 行為の哲学と意図的行為
5.2 伝統的な行為の哲学
5.3 行為の実験哲学の開始とノーブ効果の発見
5.4 ノーブ効果の発見以後の研究課題
5.5 行為の実験哲学の意義
第6章 道徳の実験哲学1――規範倫理学[鈴木 真]
6.1 トロリー問題とグリーンらの脳科学研究
6.2 脳科学的知見の規範的含意
6.3 実験哲学における論争――直観性の扱いとモデルの一般性
6.4 脳科学の手法を使った実験哲学と道徳判断研究
第7章 道徳の実験哲学2――メタ倫理学[太田紘史]
7.1 はじめに
7.2 素朴客観主義を探る
7.3 素朴相対主義を探る
7.4 他のさまざまな研究
7.5 おわりに
第8章 社会心理学から見た実験哲学[唐沢かおり]
8.1 はじめに
8.2 実験哲学のプロジェクトと心理学
8.3 心的過程を問うことの意義
8.4 質問紙によるデータ収集に伴う諸問題
8.5 おわりに――人に尋ねた結果から概念について語ることをめぐって
第9章 成果と展望[鈴木貴之]
9.1 実験哲学研究の成果
9.2 実験哲学に対する批判
9.3 実験哲学研究の展望
あとがき[鈴木貴之]
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Bevel
mtht
おちこち
Akiro OUED
buuupuuu
-

- 電子書籍
- ひとりひとり 講談社の創作絵本
-
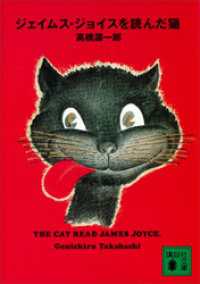
- 電子書籍
- ジェイムス・ジョイスを読んだ猫 講談社…
-

- 電子書籍
- 来世を誓って転生したら大変なことになっ…
-

- 電子書籍
- 月刊Gファンタジー 2020年12月号…
-
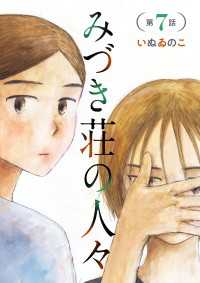
- 電子書籍
- みづき荘の人々【分冊版】 7




