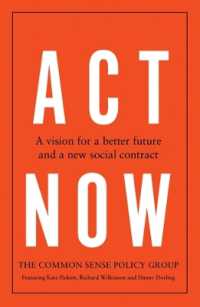内容説明
第1章でAI・ロボット法に関する見取り図を示した上で、第2章以下ではQ&A方式でAI・ロボットの重要問題についてコンパクトに解説。憲法分野、民事法分野、刑事法分野、行政法分野、知的財産法分野、国際問題といった伝統的な法分野の観点から重要問題を洗い出し、「空中戦」を避けて可能な限り実定法に則した解説を行う。
目次
第1章 AI・ロボット法総論
1 はじめに
2 AI・ロボットの概念
3 AI・ロボットのインパクト
4 本書の構成
第2章 憲法分野
Q2─1 AI・ロボットに憲法上の権利は認められますか。技術の進展に応じて、憲法上の権利に関する議論は変わりますか。
Q2─2 AI・ロボットは、プライバシーとの関係で問題を引き起こしませんか? 特に、家庭用ロボットやAIを使ったプロファイリングにはどのような問題があるでしょうか。
Q2─3 AI・ロボットは、平等原則の関係ではどのような問題がありますか?
Q2─4 AIを活用した行動ターゲティング広告などは憲法上どのような問題がありますか?
Q2─5 AI・ロボットは、デジタルゲリマンダリングとどのような関係がありますか。
第3章 民事法分野
Q3─1 AI、ロボットが関与した契約において、その効果は誰に帰属すると考えればよいですか。例えば、AIを搭載したロボットに自転車の購入を指示したところ、予想外にもこのAIによって自動車を購入する契約が締結されたという場合、利用者にその効果が帰属することになるのでしょうか。
Q3─2 AI・ロボットによって引き起こされた不法行為について、AI・ロボット自体に不法行為に基づく損害賠償責任を追及できますか。また、AI・ロボットの利用者に対して責任追及できますか。
Q3─3 AI・ロボットと製造物責任について教えてください。
Q3─4 AI・ロボットと欠陥について教えてください。
Q3─5 日本における自動運転の現状および民事上の法的論点の概要について教えてください。
Q3─6 AIを利用したソフトウェア開発を委託する契約を締結するにあたり、どのようなことに気を付ける必要があるでしょうか。
第4章 刑事法分野
Q4─1 ロボット・AIが犯罪に関わった場合、誰がどのような刑事責任を負うことが考えられますか。
Q4─2 自動車の自動運転により事故が発生した場合に、運転者、設計者、製造者はどのような刑事責任を負うことが考えられますか。
Q4─3 自動運転車による死傷事故が発生した場合に、プログラムの設計者や製造者が刑事責任を負わない場合とは、どのようなときですか。
Q4─4 AIによる犯罪予測(予測警備)とはどのようなものですか。
第5章 行政法分野
Q5─1 AI・ロボットの活用が見込まれる行政分野には、どのようなものがありますか。
Q5─2 行政分野でAI・ロボットを導入する場合、民間分野と比較してどのような点に注意する必要がありますか。
Q5─3 AI・ロボットは従来の法の世界では予定されていない技術であるため、その開発・製造・利用は行政が関与する領域ではありませんでした。これまで行政はどのようなときに、どのような目的で、どのような手法で技術や市場に関与してきたのですか。
Q5─4 AI・ロボットに関する規制が不明確な場合や規制を受ける場合にどのような制度を利用することができますか。
Q5─5 AI・ロボットの技術が実用化された場合、その安全性を確保するためにどのような行政による関与手法が用いられる可能性があるのでしょうか。
Q5─6 自動運転について、行政規制との関係で注意すべき法規制はありますか。
Q5─7 AI・ロボットは電気用品安全法の電気用品に該当しますか。
ほか
-
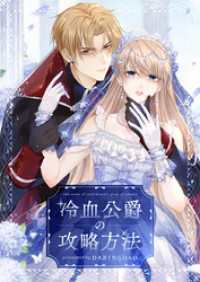
- 電子書籍
- 冷血公爵の攻略方法【タテヨミ】第98話…
-
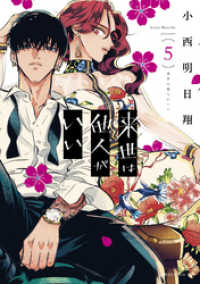
- 電子書籍
- 来世は他人がいい(5)