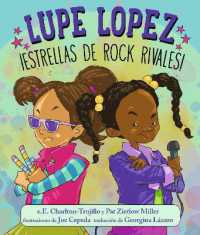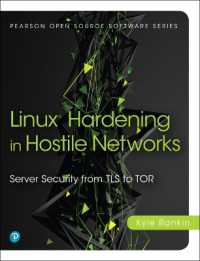内容説明
いま家族が抱える“ひきこもり”の問題を解決するために――
経験者や支援者が徹底解説。
<最近、ひきこもり問題は事件の多発化が目立ち、両親や当人の高齢化問題も浮上し、
解決困難な社会問題になりつつあります。
本人が親や応援者と対話することの重要性が高まる中、その一翼を担う形で「ひきこもり大学」は
活動を続けています。今後ますます「ひきこもり」支援が広がり、?ネガティブなイメージ”だった
「ひきこもり」に共感の輪が広がっていくことを願って、私たちは本書を執筆しました。〉寅(ひきこもり大学学長)
ひきこもりたちは何を?見て”いるのか!?
親子で実践!
ポジティブに捉えることで見つかる一人ひとりの「価値」と「幸せのカタチ」。
目次
はじめに
第1時限目 学長からの「開学メッセージ」
第2時限目 マスコミ学部 ジャーナリズム学科
第3時限目 外こもり学部 ライフスタイル・シフト学科
第4時限目 KHJ家庭関係学部 母親の気づき学科
第5時限目 回復学部 母と娘学科
第6時限目 ビジネス学部 アフィリエイト学科
第7時限目 ひきこもり対話学部 ファシリテーション学科
第8時限目 発達障害学部 ピアサポート学科
第9時限目 セルフヘルプ学部 アダルト・チルドレン学科
おわりに
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
昌也
1
本書を通しての統一した定義に関する記述はなし。 有馬知子の記述から p48「「ひきこもりかそうでないか」の分水嶺は結局、外形的な要素ではなく、本人の「生きづらさ」だと私は考えています。社会になじめていないという違和感や、他人への恐怖心をいだき、社会に対して自分を閉ざす人は、ひきこもり、またはひきこもりの「ようなもの」だと自分を認識しています。逆に、外見上は内閣府の定義に該当しても、生活に充足し、社会への違和感がない人には、当然ながら「ひきこもり」という自己認識はまったくありません。2021/02/21
Tatsuhiko Teramatsu
1
★★☆☆☆2020/11/15
A.T
0
★★★☆☆ まずは自分のひきこもりに対する固定概念をなくさないといけない。彼ら学校や職場に行かなくても、必要最低限の外出もするし、全員が引っ込み思案というわけではない。ひきこもりの人がいる家族は、ひきこもりがいることを恥ずかしがったりしないこと、当事者の言うことを受け容れ、かつ上辺の言葉じゃなくて本音で会話する、どうにかしてやらないといけないという考えを変える、など勉強になることが多くあった。ひきこもりの人の多くが発達障害の可能性を持っており、特性を理解してその特性を活かしていけるような支援が必要。2023/09/29
影慶
0
当事者でない人が当事者として語る事の危険性に留意したい(ひきこもりを名乗るのに資格はいらない)。欺瞞や偽善に敏感な「本物」のひきこもりはこうした団体をどう思うだろうか。2023/04/28
TOMTOM
0
一番は「外こもり」という概念に出会えたこと。家の中に居場所がないから外に出る。たまたまその方はまっとうな道に進んだからよかったものの、一歩間違えたら非行の道に行ったんだろうな。2022/02/27
-
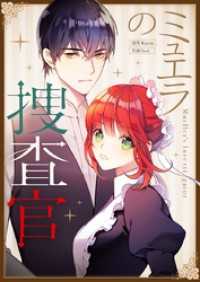
- 電子書籍
- ミュエラの捜査官【タテヨミ】第98話 …