内容説明
異郷に暮らし、過去の記憶に苛まれる4人の男たちの生と死。みずから故郷を去ったにせよ、歴史の暴力によって故郷を奪われたにせよ、移住の地に一見とけ込んで生活しているかに見える移民たちは、30年、40年、あるいは70年の長い期間をおいて、突然のようにみずから破滅の道をたどる……。語り手の〈私〉は、遺されたわずかの品々をよすがに、それら流謫の身となった人々の生涯をたどりなおす。〈私〉もまた、異郷に身をおいて久しい人だ。個人の名前を冠し、手記を引用し、写真を配した各篇はドキュメンタリーといった体裁をなしているが、どこまでが実で、どこまでが虚なのか、判然としない。
本書は、ゼーバルトが生涯に4つだけ書いた散文作品の2作目にあたる。英語版がスーザン・ソンタグの称讃を得て、各国語に翻訳され、ドイツではベルリン文学賞とボブロフスキー・メダル、ノルト文学賞を受賞した。
堀江敏幸氏による巻末の解説「蝶のように舞うぺシミスム」から引用する。「作家の極端なぺシミスムが読者にかけがえのない幸福をもたらすとは、いったいどういうことなのか? ゼーバルトの小説を読むたびに、私はそう自問せざるをえなくなる」。
-

- 電子書籍
- 評価と報酬の経営学~アイツの査定は高す…
-
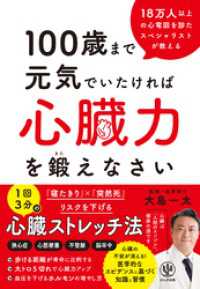
- 電子書籍
- 100歳まで元気でいたければ心臓力を鍛…
-
![別冊フレンド 2021年1月号[2020年12月11日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0933761.jpg)
- 電子書籍
- 別冊フレンド 2021年1月号[202…
-

- 電子書籍
- 平成愚連艦隊 大作戦!戦艦大和救出編 …




