- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
川、海、濠、湧水、池、用水。東京は下町から郊外まで、豊かな水辺をもっている。この都市の象徴=隅田川、文明開化のモダンな建築群が水辺を飾った日本橋川、世界にも類を見ない豊かな自然環境を保有する皇居・外濠、凸凹地形と湧水が目白押しの山の手、水辺をたどれば古代の記憶に触れることができる武蔵野……本書は東京各地をめぐりながら、この魅力的な水都の姿を描き出す。『東京の空間人類学』から35年、著者の東京研究の集大成がついに刊行!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
59
隅田川やベイエリアといった海に面した所から山の手、杉並といった一見水から離れた所、そして日野まで、水の都としての東京を論じた一冊。先に読んだ『東京の空間人類学』が総体としての東京を扱っているのに対して、本書では場所場所を断片的に取り扱う事によって、東京の水都としての一面を浮かび上がらせる構造となっている。あと水都としてだとどうしても深川等の海の方に目が行きがちだけど、川や上水といった水の流れに目を向けることによって山の手の方もその範疇に含めているのは新しいかな。東京の新たな一面を浮かび上がらせる本でした。2020/11/16
パトラッシュ
58
古地図を見ると、江戸の町は川と濠と海をつないだ水路を縦横に張り巡らしているのがわかる。世界最初の百万都市は水運を基礎に発展したのだ。これに神田川や玉川上水、多摩の湧水まで加え、江戸から東京へと続く4世紀に及ぶ発展が水との深い関りの上に成立していることを論証する。何よりも海外で「水都」と呼ばれるヴェネツィアやアムステルダムなどと異なり、水が流れる地形や地質を徹底的に利用して独自の進化を遂げたプロセスは頷ける。ウオーターフロントとは海岸だけでなく、後背地も含めた都市全体で成立するのだと理解しなければならない。2021/01/24
yyrn
30
川や海の利用を含め、都市は陸地の地形と共に発達し歴史を積み重ねてきたが、近代の発達した技術のおかげで街はその面影を失いつつある。よく探せばまだ見つけられるが、日々の生活に忙しい人にはなかなか目にとまらない。だからブラタモリなどの番組で教えられるとハッとすることがある。江戸・東京に関する本はそれこそ腐るほど読んできたので、この本で新たな知識を授けられたということはあまりないが、武蔵野や多摩まで広げて様々な情報が丁寧に示され、それらがカチッとはまって巨大都市、東京の成り立ちと全容が鮮明になった、と思う。良書。2020/12/15
kk
26
人と水との関わり合いという視線から、東京の越し方とポテンシャルを問い直す一冊。都心・下町の河川や水路などの発展と役割に着目して東京をヴェネツィアと重ねて論じる発想に感心。また、従来の「江戸=水都」論を超えて、武蔵野・多摩地区における湧水や用水などの人々の生活・文化への影響にも注目。都心部だけでなく有機的な地域としての人と水の関係を考えるという新しく大きな視点。「武蔵野辺りってのは元々たいがいは雑木林か草っ原」なんて思ってたkk、己の不明を恥じ入るばかり。知的好奇心を大いに唆られました。2023/06/02
雲をみるひと
14
地形、中でも河川や水の流れに主眼を置いた東京の考察本。隅田川や日本橋川と言った川のみならずベイエリアなど水にまつわるエリア毎にろんじらている。研究が進んでいる旧江戸市街地や城東地区の章は新説も交えながら深掘りされているが、山手西部や多摩を扱った章は作者の個人的体験がベースな場合が多く毛色が異なる。 これらのエリアを深掘りした次作にも期待したい。2020/12/15
-

- 電子書籍
- 咎狗の血【ページ版】12 JAMTOON
-
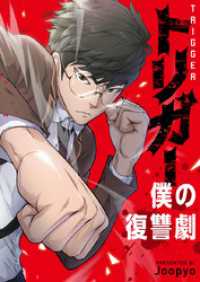
- 電子書籍
- トリガー~僕の復讐劇~【タテヨミ】第3…
-
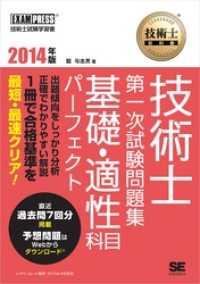
- 電子書籍
- 技術士教科書 技術士 第一次試験問題集…
-
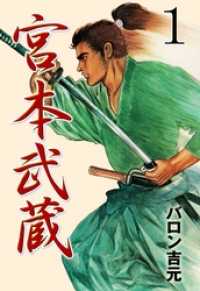
- 電子書籍
- 宮本武蔵1巻 マンガの金字塔
-
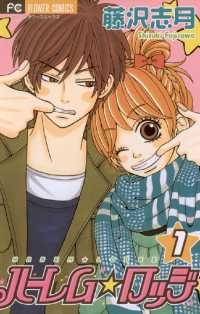
- 電子書籍
- ハーレム☆ロッジ(1) フラワーコミッ…




