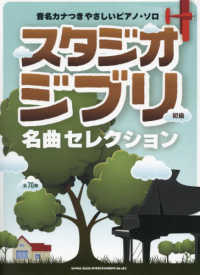内容説明
日本で「メディア論」はどのように覚醒したのか。空前絶後の大阪万博をはじめ、その契機となった出来事に焦点をあてる。大学における人文知の伝統のみならず、情報環境のグローバルな変容に鋭敏な芸術家や建築家の創造知、CATVやミニFMなどに魅了された人びとの実践知とも不可分に結びついた、メディア論的思考の地脈を探る。
目次
はじめに
I メディア論の地層
第1章 マクルーハン、環境芸術、大阪万博――一九六〇年代日本の美術評論におけるマクルーハン受容
1 マクルーハニズムの「第三の軸」
2 環境芸術、大阪万博との相互連関
3 「環境芸術論」から「メディア論」へ
4 祭りのあと
第2章 メディアのなかの考現学――アカデミズムとジャーナリズム、エンターテインメントの狭間で
1 新しいジャーナリズムとしての考現学――一九二〇年代
2 マーケティング的考現学の萌芽――一九六〇年代
3 芸能追跡に併存する民俗学/考現学的視座――一九六〇~七〇年代
4 考現学ルネッサンス――一九八〇年代
5 キッチュな考現学へ――一九九〇年代以降
第3章 インターネット前夜――情報化の〈触媒〉としての都市
1 マスメディアとインターネットのあいだ
2 雑誌が都市文化を牽引していた一九九〇年代
3 カラオケボックス――情報化と郊外化の実験室
4 モバイルな私生活化
II メディア・リテラシー論の地層
第4章 放送文化の民俗学――六輔さすらいの旅、その射程
1 実験放送という原点
2 「王道」から「異端」へ――放送史のなかの永六輔
3 技術と表現のシナジー――『六輔さすらいの旅 遠くへ行きたい』
4 一望の荒野へ――放送文化の民俗学
第5章 送り手のメディア・リテラシー――二〇〇〇年代の到達点、一〇年代以降の課題と展望
1 地方局のショッピングモール進出
2 「送り手のメディア・リテラシー」の到達点
3 協働型メディア・リテラシーの課題と展望
4 情動、アーキテクチャ、リテラシー
第6章 ポストテレビ、ハラスメント、リテラシー――地上波テレビとインターネット動画の関係史
1 地上波テレビとネットテレビの乖離
2 『めちゃイケ』とBPOとの応酬
3 テレビとネットの相互作用
4 ネット動画に溢れかえる「テレビ芸」
III メディア・イベント論の地層
第7章 大阪万博以後――メディア・イベントの現代史に向けて
1 メディア・イベントの範例と革新
2 範例的メディア・イベントとしてのタイム・カプセル――松下館
3 ハプニングとしてのテレビジョン――電気通信館
4 2025大阪万博へ
第8章 メディア・イベントの可能態――藤幡正樹《Light on the Net》(一九九六年)を解読する
1 メタ・モニュメント――藤幡正樹『巻き戻された未来』(一九九五年)より
2 祝祭としてのメディア・イベント――祐川良子「インターネットメディアにおける美術作品の試みと考察」(一九九七年)より
3 《Light on the Net》の現代的意義
第9章 遍在するスクリーンが媒介する出来事――メディア・イベント研究を補助線に
1 スクリーンと映像が遍在する二〇二〇年代
2 メディア・イベントからスクリーン・スタディーズへ
3 メディア・イベント研究の到達点と課題
4 スクリーンに媒介された集団の雑種性、複数性をどうやって捉えるか
5 カッツからタルドへの遡行
IV パブリック・アクセス論の地層
第10章 DIYとしての自主放送――初期CATVの考古学
1 趣味文化としてのCATV
2 自作趣味×婦人会活動――郡上八幡テレビ
ほか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
お抹茶
tkm66
チャーリイ
-

- 電子書籍
- 幼馴染の腹黒王太子、自分がテンプレ踏ん…