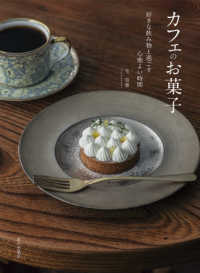- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
経営者と従業員の利害は、どのように調整できるか。労働者の団結や労使協調、あるいは経営参加という現代の労使関係の理論はどのように生まれたか。英国のコレクティブ・バーゲニング、米国のジョブ・コントロール型労使関係やフランスの自主管理思想、ドイツ型パートナーシャフト、日本型雇用など、世界中で模索され、実践されてきた労使関係の理想と現実とは。労働イデオロギーの根源を探訪し、働くということを根本から考える一冊。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Francis
19
労働法の専門家、濱口桂一郎さんと「年金不安の正体」海老原嗣生さんの共著の形式だが実際には濱口さんの本。濱口さんが英米仏独そして日本の労使関係の古典の内容を説明し、これらの国の労使関係がどのような歩みをたどったかを解説。「労働・雇用システムは歴史的な経緯で成り立つもの」と書かれているが本当にその通りだと思う。日本では類書はマルクス主義対反マルクス主義右派の不毛な対立になりがちなのでこの濱口さんの本は大変ありがたい。クリスチャンとしてはドイツのフォン・ケテラー神父様の本が取り上げられているのが良かった。2020/10/22
venturingbeyond
14
期末考査期間中に、年休をとって読了。英・米・独・(ほんの少し)仏の労使関係の特徴とその長所・短所を労働政策論・労使関係論の古典を引いて考察する一冊。濱口先生の本に外れなしの良書。個別の論点は直接あたってもらうとして、一冊を通じて(勿論これまでの著作からも)まずおさえておくべきは、労使関係の歴史的な経路依存性。地べたの運動の勃興・拡大・制度的定着の背後には、社会構造の違いや歴史的偶然が存在し、どこか国の労働政策や労使関係の理想像を社会的文脈を無視して移植すれば解決とはいかないという点が出発点。2020/12/04
Mc6ρ助
11
雑誌掲載時の「原点回帰」が本の内容を端的に表す。労働研究(なぜ労働学、という学がないのか素人には判りかねぬ)古典を参照する。日本は昔も雰囲気、ムード、やってるフリで世の中が動く。『・・かつては「わが国の労働争議が年々労働組合の季節闘争として、そしてこの季節闘争は共同闘争、統一闘争、さらにまたしばしばいわれるようにスケジュール闘争の形において」(106頁)行われていました。藤林は「なにゆえにこのような争議が発生するか」と問い、「これは一種の雰囲気闘争である」「ムード闘争である」と答えます・・。(p201)』2021/05/15
ザビ
10
大学の講義のような一冊で、軸となる内容は世界の労働組合の変遷。この分野を専門的に勉強する人にはいいかも。労働組合の元祖はイギリスの社外集合取引、労使は経営共同体のパートナーシップを基礎にしたドイツ、激しい労使交渉を繰り返してきたアメリカ。ドイツのパートナーシップには個人の主体性を尊重する宗教観が根底にあるんですね。企業内労働組合が主体の日本は世界的にはかなり特殊で、それが故に左翼的なイデオロギー論争が強いことは理解できた。著作では「ムード闘争」と批判的に呼ばれている。2021/08/10
復活!! あくびちゃん!
9
「働き方改革」というタイトルに惹かれ、気楽に手にとっては見たが、内容はヨーロッパを中心(最後に日本が少し)に労使関係の古典の内容を説明し、当時の状況を説明したかなり硬派なもの。読んでいてクラクラするぐらい私には合わないものだったが、唯一良かったのは、ヨーロッパでは「同一労働、同一賃金」が普通で、日本ではそうではないという理由が(歴史的背景も含め)よく理解できたこと。でも、(新書にしては)専門書すぎて、私にはついて行けましぇーん!2020/12/12
-
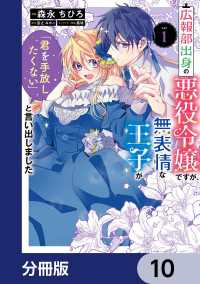
- 電子書籍
- 広報部出身の悪役令嬢ですが、無表情な王…
-
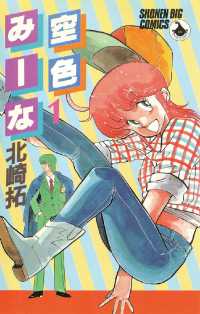
- 電子書籍
- 空色みーな(1) 少年ビッグコミックス
-
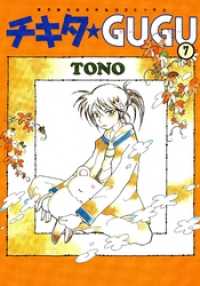
- 電子書籍
- チキタ★GUGU 7巻 眠れぬ夜の奇妙…
-
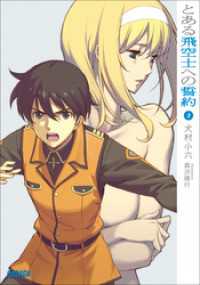
- 電子書籍
- とある飛空士への誓約3(イラスト簡略版…