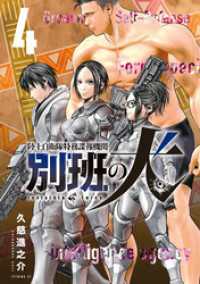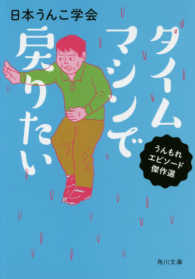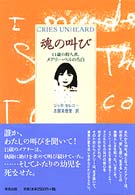内容説明
中世から名が残る美しい南イングランドの農地1400ヘクタールを再野生化する――
農薬と化学肥料を多投する農場経営を止め、所有地に自然をとりもどすために、野ブタ、鹿、野牛、野生馬を放ったら、チョウ、野鳥、めずらしい植物まで、みるみるうちに復活。その様子を驚きとともに農場主の妻が描いた全英ベストセラーのノンフィクション。
日本同様、農村人口が減り続ける英国での壮大な実験の記録。
『この10年でエコロジー本の指標となる1冊』(サンデー・タイムズ紙)
『2018年、最もインスピレーションを与えてくれた1冊』(デイリー・メール紙)
米国でも大反響!
スミソニアン誌10ベストサイエンスブック2018
フォーブス誌10ベスト環境ブック2018
目次
はじめに
第1章 樹齢550年の巨木と一人の男
クネップの歴史とオーク
庭園から農場へ
菌根と近代農業
忘れ去られたオーク
オークと生物多様性
第2章 私たちが農場経営を諦めるまで
農場拡大を夢見て
農場経営の破綻
新しい道筋
第3章 農地が生き物であふれかえる
躍動する生き物たち
土壌改善に着手する
庭園になくてはならないもの
ダマジカを放つ
第4章 オランダ自然保護区の衝撃
オランダの再野生化
草食動物と生物多様性
森ができる前のヨーロッパ
オーストファールテルスプラッセンでの実験
草食動物が生み出す奇跡
第5章 再野生化、実現までの険しい道のり
再野生化への野望
繰り返される「視察」と「話し合い」
根強い閉鎖林冠説
花粉学者の主張
原始ヨーロッパに広がる草原
ヨーロッパ人と森
追い風が吹く
第6章 野生のウシ、ウマ、ブタを放つ
希少品種のウシを放つ
野生馬が加わる
イノシシの代役
ブタの土壌改良能力
第7章 近隣住民の不満噴出
プロジェクトの停滞
低木とオークの苗木
自然保護活動家の矛盾
萌芽更新と低木
地元住民との軋轢
自然保護より農業生産
第8章 プロジェクトの危機
憎まれ役の雑草
やまない誤解と偏見
「不自然」なのか「自然」なのか
第9章 数万匹のヒメアカタテハの襲来
動物・植物学者が集結
「再野生化」の定義
鍵となる生物種
再野生化への懸念
セイヨウトゲアザミVSヒメアカタテハ
第10章 イリスコムラサキとサルヤナギとブタ
希少な鳥とコウモリがやってきた
孤独なクジャク
再野生化が勢いづく
イリスコムラサキの飛来
2足す2が5になる
第11章 ナイチンゲールの哀しみ
姿を消したナイチンゲール
復活の兆し
再び姿を消したナイチンゲール
第12章 コキジバトの鳴き声が消える日
コキジバトの減少要因
個体数を増やせ、「コキジバト作戦」
孤立する自然保護区
打ち捨てられる「自然保護」
第13章 洪水と川の再野生化
記録的豪雨と川の氾濫
水路造成の歴史
張り巡らされる排水管
堤防建設以外のやり方
2.5キロの川の再野生化
渓谷に暮らす住民たちの選択
第14章 戻ってきたビーバー
ミズハタネズミとビーバーの深い関係
ビーバーの並外れた創造力
イギリスでビーバーを放つ
ドイツでの成功事例
野生ビーバーの発見
第15章 自然保護と経済
意外な副産物
穀物飼料不使用へ
ウシとウマの共存関係
自閉症の動物学者とウシ
ウマの頭数制限
草食動物と植生遷移
第16章 土は生命
小型哺乳類の増加
あっという間に増えたチョウとガとハチ
働き者のミミズ
人工肥料による環境破壊
ミミズによるクネップの土壌改善
グロマリンは二酸化炭素を減らせるか
第17章 ヒトと自然
自然への関心を育む
心身に効く「自然」
生き物がもたらす喜び
自然な姿とは何か
再野生化とビジネス
自然保護の光と影
クネップ年表
出典
参考文献
訳者あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Bashlier
たまきら
宇宙猫
ぽてちゅう
ykshzk(虎猫図案房)