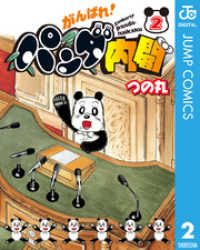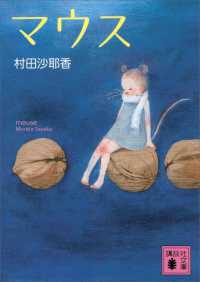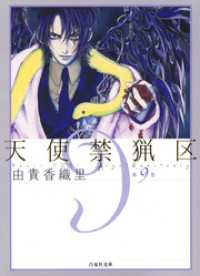内容説明
1953年のテレビ放送開始は、政治家とメディアの関係を大きく変えた。政治家たちは出演してPRに努める一方、時に圧力をかけ、報道に影響を与えようとする。佐藤栄作政権で相次いだ放送介入、田中角栄が利用した放送免許、「ニュースステーション」の革命、小泉フィーバー、尖閣ビデオ流出事件、そして橋下徹のツイッター活用術まで、戦後政治史をたどり、政治家と国民とのコミュニケーションのあり方を問い直す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
香取奈保佐
45
日本政治史をメディアとコミュニケーションの観点から俯瞰した一冊。大衆とどう向き合うか悩みながら、メディアをいなす政治家たちの苦労が浮き彫りになっていて非常に面白かった。民衆に媚びすぎる政治は近視眼的になり、理解されない政治は動きがとれない。無党派層が増えてきてから、それを取り込むためのコミュニケーションの重要性が飛躍的に高まっていたのが印象的だった。インターネットについてもきちんと整理して記述していたのは良かったと思う。大学の課題が片付き、ようやく読書に専念できる。うれしい。後で書評を書きます。2015/01/24
coolflat
20
時の政権がメディア対策を重要視したのは60年安保からだと言う。主流メディアが新聞からテレビに移り変わる転換点で、テレビにより岸政権は退陣に追い込まれた。昨今の状況としては、政策論争よりも、政治家個人のキャラクターが重要視されている。小泉の様に上手くキャラを演じられなければ、森、安倍(第一次)、福田、麻生の様に、退陣に追い込まれる。それを踏まえたのか、キャラの演じられない安倍(第二次)は、食事会と称してメディア上層部を懐柔し、一方ではNHK会長を身内で固め、批判する局には電波停止をちらつかせて統制を図る。 2016/07/06
ぐうぐう
20
テレビというメディアに放送免許が交付された1952年から現在に至るまで、政治がいかにメディアと関わってきたか(それは同時に、メディアがいかに政治と関わってきた、でもある)を考察する『日本政治とメディア』。驚かされたのは、テレビが登場してすぐに、政治家側が積極的にその新しいメディアを利用していたことだ。政治家の予見は当たり、テレビが新聞やラジオを凌駕し、大きな影響力をもつメディアに成長するにつれ、政治家はさらにテレビを利用しようとする。(つづく)2014/10/11
スプリント
7
政治とメディアの力関係が徐々に変容していく様がよくわかります。そして現代の政治家とテレビ・新聞メディアとネットの三つ巴状態へとつながるわけですが顔の見えないネットの影響力がこのまま高まり続けることへの危険性を感じます。2014/12/13
ナツメッグ☆
6
非常に興味深い論考。テレビの果たしてきた役割、これからの展望が概観できる。ただキャラ化する政治家のテレビへの露出にはもう少し突っ込んで欲しかった。功罪も含めて今少し詳細な考察が必要かと。SNSが伸長してきた今日、テレビの果たす役割が同変容していくのか見守っていきたい。2014/11/09