内容説明
イタリア・フィレンツェ郊外の小さな美術館で出会った一つの謎めいた板絵。それは死んだはずの赤ん坊をよみがえらせた聖人の奇跡を描いたものだった。この「嬰児復活の奇跡」と、その上位テーマたる「狂気の母」が、著者を思索の旅に招き入れる。聖餐・聖遺物といったキリスト教文化圏特有の信仰形態や、遡って古代エジプト、ギリシア、ケルト文化にも見られる「死と復活」の主題。これら多くの図像や史料を読み解きながら西洋精神の根幹を成す「死と復活」の思想の本質と、キリスト教の深層に肉薄する。
目次
はじめに──生き返った赤ん坊
死んだ赤ん坊をよみがえらせる奇跡
第一章 「嬰児復活の奇跡」と聖遺物
「嬰児復活の奇跡」の図像
奇跡のエピソード──列聖審査のために
「post mortem」──死せる聖人の奇跡
遺体が保ち続ける力と「聖遺物」
巡礼と、病を癒す聖遺物
一神教における聖遺物の矛盾点
過熱する聖遺物崇敬
煉獄とは何か
煉獄と贖宥状をめぐる論争
盗まれる遺体
切り刻まれ、食べられる遺体
第二章 聖餐とカニバリズム
血を流す聖体
四福音書は「最後の晩餐」をどう記述したか
「Q文書」と四福音書
記述内容の違いから浮かび上がるもの
それはパンか、それとも肉か
死海文書とミサの原型
補強されていく聖変化
聖体解釈をめぐる論争
聖マルティヌスと聖フランチェスコ
「ボルセーナのミサ」と異端者たち
二人の宗教改革者を隔てるもの
カニバリズムの一形態としての聖餐
共同体の拒否反応
プロパガンダ図像としての「血を流す聖体」
第三章 聖杯伝説と生贄の祭儀
不死の薬としての聖体
アーサー王と聖杯伝説
アリマタヤのヨセフ、あるいは聖杯の守護者
不死をもたらす聖杯──キリストの犠牲的な死
エジプト神話にみる死と復活
ミトラ教にみる死と再生
過越の祭の生贄
初子の生贄としての「子殺し」
豊穣をもたらす聖体
第四章 子殺しの魔女とケルトの大釜
子殺しはどう描かれたか
産婆への嫌疑
子殺しの魔女
わが子を殺すメデイア
「再生のために煮る」メデイアと魔女
ケルト神話の「再生の大釜」
第五章 ディオニューソスと「洗礼による死」
酒の神ディオニューソス
冥界と結びつくディオニューソス
マイナデスによるバラバラ殺人
トランス状態と殺戮
生贄をバラバラにする収穫神
「Agnus Dei」と「命の泉」
生贄となる神自身
キリスト─オシリス─ディオニューソス
それは煮て、焼かねばならぬ
それはいったん水で死なねばならぬ
洗礼──異教徒としての死と再生
十字の切断痕
第六章 若返りの釜──グノーシス、錬金術、アンドロギュヌス
「聖杯の文化」の発展
「回春炉」の錬金術
錬金術とアンドロギュヌス
多神教と一神教の融合の試み──ルネサンス・ネオ・プラトニズム
ヘルメス文書と錬金術的「合一」
グノーシス主義とイエスの肉体
ルネサンス・ネオ・プラトニズムとアンドロギュヌス体
君主称揚図像としてのアンドロギュヌス体
レオナルド・ダ・ヴィンチとフォンテーヌブロー派
レオナルド〈洗礼者ヨハネ〉の両性具有性
不老不死となった王
おわりに──記憶としての図像
註
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆずこまめ
東雲
遊未
T.Y.
坂口衣美(エミ)
-

- 電子書籍
- 安全運転で転生(トバ)します【単話売】…
-

- 電子書籍
- 美術世界 第十六巻 【復刻版】
-
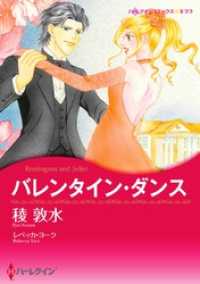
- 電子書籍
- バレンタイン・ダンス【分冊】 4巻 ハ…
-

- 電子書籍
- 医者から赤ちゃんが難病といわれた話4 …
-
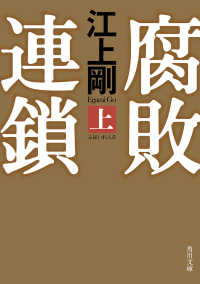
- 電子書籍
- 腐敗連鎖 上 角川文庫




