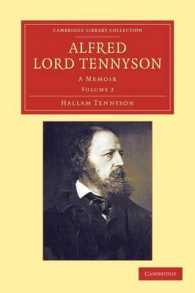内容説明
学者が紹介する多種多様な自然の生き物の成長のかたちから、人間にとっての「学ぶこと」や「大人になること」の意味を考える。
子どものほうが大人より大きなカエルやペンギン、溺愛した子を突然突き放すキツネ、遊びから狩りを学ぶライオン、大小2つの種を持つオナモミ、踏まれたら立ち上がらない雑草――。
自然界の動物や植物は、さまざまな個性をもって「成長」していきます。
一方で、人間の「成長」は、得てして順番を競ったり、平均値と比べたりと、画一的なものさしで計られることが多いようです。
本書では、そんな人間の「成長」について、驚くほど多様で面白い生き物の成長の仕方から学ぶことを試みます。
著者は『生き物の死にざま』『面白くて眠れなくなる植物学』など、自然科学系のベストセラー著書多数の稲垣栄洋氏。
中学・高校入試問題の採用数ナンバーワンの著者による、生物学的な知的好奇心をくすぐり、“学ぶこと”や“大人になること”の意味を考えさせられる一冊です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mae.dat
173
凄く良かった。本文は読み易いのに、内容は深いよ。 タイトル通り生物が成長する様子をテーマに据えており、様々な、時にはヒトからするとおぞましい様な生態をしてるものも収録されていますが、その紹介がメインではございません。 それぞれの生物がどう環境に適応してきて、そんな成長過程を獲得したのか?とか。本能と学習による行動の違いとは?とか。多様な個性は生存戦略的にどう作用するのか?そしてヒトは?などなど、めたんこ示唆に富んでます。 稲垣せんせー、またまた面白く興味深い本をありがとうございます。( ¨̮ )。2021/03/08
kinkin
116
大人と子供、遊びと学び、ふつうとは等について動物や植物と比較しながら解説されている。著者の本はよく読むが、いつもながら平易に書かれているので読んでいても疲れない。人間というのは動物界全体で見れば稀有な存在で知能も高い。しかし出産や子供が自立して育つにはかなりの時間が必要ということ、ハサミムシの母親の子育てのことは別の本で読んだことがあるがほんとうに健気な話だ。自然界から人間が学ぶことはまだまだあるだろうし、これからも見つかると想う。挿絵も優しい。図書館本2021/12/19
trazom
85
稲垣先生を読むのは「敗者の生命史38億年」「生き物の死にざま」に続く3冊目。タンポポから、クモ、トンボ、カワウソ、キツネに至るまで多彩な事例が紹介されているが、「多くの生物は「本能」で子育てをするが、哺乳類は、それを「知能」に委ねた」ことを踏まえて、どうしても「子育てとは」という教育論として読んでしまいがちになり、そうすると面白さが半減する。むしろ、植物学者の先生らしく「踏まれた雑草は立ち上がらない」という話の方が印象的。「踏まれたら立ち上がれ!」という人間の勝手な思い込みに対する痛烈なアイロニーがある。2020/09/14
モリー
50
人間ほど子育て期間の長い動物はいないという。人によっては、20年以上子育てする親もざらにいる。これは、動物界では異例の長さなのだ。おじいちゃん、おばあちゃん、つまり、親より前の世代が生きてるということも動物界では特異なことであるらしい。全ての生物から共通項を括りだすならば、子供を産んで、死ぬということだ。だが、大人になるまでの期間や子育ての方法は多様である。生物学的に考えれば、それは種を存続させるための、それぞれの戦略と言い換えることが出来るだろう。さて、人間は何故これ程長く子育てしなければならぬのか。↓2024/06/16
森の三時
43
数多の生物の中でも人間はやはり特異な位置にいると思いました。他の生物の成長や種の保存についての多様性を知ることは、人間についての硬直的な考え方を見直す契機にもなります。本能で備わっていることで対応して生きていく生物は直ぐに大人になれる一方、後から獲得する知能で対応する、すなわち生きていくために学習が必要な人間は、子育て期間が長く大人になるまでに多くの時間を要する。厄介なことではあるが、それこそ人間たらしめることだとしたら、大人は子どもに子ども時代を急かしてはいけないと思いました。2022/04/18
-

- DVD
- 影武者〈普及版〉