内容説明
我が子の「教育」が苦しい――それはあなた一人の責任ではない。「クラス全員を企業家に育てる」教育にNOと言おう! どうやら企業人や政治家、官僚たちは、日本の経済的低迷を教育で挽回しようとしているようだ。まるで、「最小限のコストで最大限の商品(人材)を納品しろ」と言わんばかりである。そんな社会を生きる私たちの子育て――とりわけ教育は、じつに悩ましい。なぜこんなにも苦しいのか。しかし本書は、「それはあなた一人の責任ではない」と説く。これは社会全体の問題なのだ。では、どうすればいいのか。本書は、明治時代から現在に至るまでの教育の歴史を振り返りながら、私たちが教育に期待すべきこと、そしてその実践の方法を試みる。これは教育学からの反抗であり、絶望に包まれた教育に対する、たしかな希望の書となるだろう。
目次
はじめに
第一章 教育家族は「適応」する
第二章 教育に期待しすぎないで
第三章 教育に世界(コンテンツ)を取り戻す
第四章 そして社会と出会う、ただし別の仕方で
おわりに
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
小鈴
24
うーん。勢いはあるんですが、読み進めると辛くなった。経済も社会も低迷して「教育」に期待をかけすぎているという批判はその通りだが、「世界と出会う」という教育って昔から言われてるんじゃないのかな。消費(享受)教育としてますが、消費=享受と定義してはたしてよいだろうか?厳密に検討してみた方がよいかも。個人的には、今のカリキュラムでも出会える子は世界に出会えるんじゃないのかな。我が子から聞く授業の話は楽しそうですよ。大丈夫。子供は強い。大人が不安なんですよね。子供に投資して元を取ろうとするから苦しいんですよ。2020/09/22
大先生
13
面白いけど、まわりくどい(苦笑)。もっと教育を「ゆるめる」必要があるという反社会的・反教育学的な教育論という発想は面白いと思いますが、結局大したことは言っていません。ビジネス社会の供給側をみたすための人材育成としての教育と捉えるのではなく、需要を増やすための教育=休日のための教育が必要って…。教育過当競争の解決策になりますかね?因みに私は子どもを私立の小中高に入れるつもりはありません(笑)。本人に素質とやる気があるなら良いと思いますが、実際は親のエゴという場合が多いと思われます。2022/01/07
はる
12
現代は「のびのび」と「きっちり」をベストミックスさせた高度に計算された緻密な子育てが要求されていて、それを実行しようと親たちは葛藤やプレッシャーを感じていると。確かに認知機能に加えて非認知機能が大事と様々な場面で強調され、教育産業からも無意識に煽られ競争は激化、都心部では塾や習い事も席取り合戦のようになっている。そういったサバイバルも子を思うが故、ということなのだが、子どもが自身の力で勝手に育つだろうという自信がないことの裏返しなんだろうな。親も悪戦苦闘しながら段々と本質が見えていくようになるんだろうか。2022/11/18
リットン
8
社会で役に立つかで判断する教育に偏ることに否定的で、教育を科目というコンテンツを介して世界を広げるものであっていいんじゃないかという主張は、すっごく共感するなぁ。とはいえ、自分も今は何にも役に立たなさそうな本をたくさん読んでそれを楽しめているけど、高校生の頃は試験に出るものだけしか絶対やらなかったし、そうでない教科はなんなら計画的に睡眠時間に充ててたし、世界を知る喜びのために美術も音楽もやりなさい!って言われても無理だったよなぁ。。でも少なくとも小中学生くらいは役に立たないこともたくさんやって欲しいなぁ2024/01/09
たらこ
6
吉川徹先生がtwitterで読んだって言っていたので読んでみた。よき消費者となるための教育。2021/08/17
-
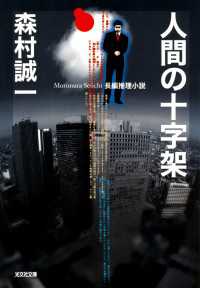
- 電子書籍
- 人間の十字架 〈1〉




