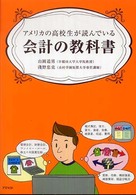内容説明
■珠玉のストラディヴァリウス21挺が東京に集結!
世界を驚かせた「奇跡の7日間」実現までの奮戦記
ヴァイオリンをこよなく愛する日本人が、たった一人で始めた「東京ストラディヴァリウス・フェスティバル」計画。誰もが「無理だ」と諫めたが、男は諦めない。
名匠ストラディヴァリが残した傑作ヴァイオリン、幻のヴィオラ、唯一のギター、希少なチェロを追って、イタリア、イギリス、スイス、日本を東奔西走。再三の門前払いにもめげず、アポなし突撃、張り込み、パーティー潜入で道を探る。
会場探し、スポンサー開拓も難航を極めるが、それにも怯まずに全力で駆け回る綱渡りの日々。「できるまで、やる」。その信念が、やがて人々の心を動かしていく。
総額210億円、珠玉の名器21挺を日本に集結させ、世界を驚かせた「奇跡の7日間」実現までの1800日戦記。
■プロジェクトリーダー必読!
「前代未聞のストラディヴァリウス・フェスティバルを、本場ヨーロッパではなく、日本でやってのけた舞台裏。クラシック関係者のみならず、プロジェクトリーダー必読の一冊だ」フレンズ・オブ・ストラディヴァリ会長パオロ・ボディーニ推薦!
歴史と伝統に裏打ちされたヨーロッパ弦楽器界の強固な門を、はるか遠く日本からやってきた若者は、愚直に叩き続ける。頑なに拒否し続けた人々の心をいかに開き、絶大な信頼を得たのか。
■ストラディヴァリウス21挺のエピソードリストを収録!
フェスティバルに集結した奇跡の21挺は、どんな人々の手を経て今に至るのか。それぞれの300年の軌跡を、カラー写真とともに辿るエピソードリストを収録。
目次
プロローグ
第1章 ヴァイオリン屋の息子
第2章 なぜストラディヴァリウスか
第3章 作戦開始
第4章 幻のヴィオラ
第5章 会場決定
第6章 点と点
第7章 スポンサーを探せ
第8章 初公開ラッシュ
第9章 前代未聞たちのパレード
第10章 コンセプトを詰め切れ
第11章 カウントダウン
第12章 展覧会開幕
第13章 走り切れ
第14章 終わりと始まり
第15章 共鳴する未来
エピローグ
21挺のストラディヴァリウス エピソードリスト
フェスティバル フォトリポート
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まろまろ
しばこ
スプリント
Susumu Kobayashi
mayumi
-

- 電子書籍
- 最強医仙の都市修行記【タテヨミ】第21…
-
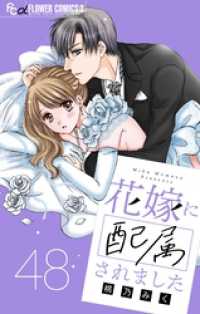
- 電子書籍
- 花嫁に配属されました【マイクロ】(48…