内容説明
深い学識で古代から江戸時代までを語りあう。
国民的作家である司馬遼太郎と、地方史・部落史・女性史など新しい視点から数々の研究を発表してきた歴史学者の林屋辰三郎というふたりの碩学による対談集。高松塚古墳で高句麗の影響を論じ、大化の改新に隋・唐帝国成立の影響を探る……。平易な語り口で、古代から江戸時代までを縦横無尽に論じています。歴史を読む楽しさを感じながら、日本について考える上での、さまざまな示唆を与えてくれる贅沢な1冊です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キムチ
43
帯にある知的ぜいたくとは言い得て妙。35年前の対談ながら古さを感じさせない練り合わされた知識の豊かさを感じさせる。そら、当時の巨頭のがっぷり4つだもの…あとがきで林屋さんと陳氏が面白く感想を述べている。古代史観は種々あれど語られている雑感は共感を持っ、遠古代、近古代。東アジアの標本みたいな日本、天皇のルーツ、鎌足、武家政治等々。咄の味わいは深く、興趣に満ちている。2016/06/20
Akihiro Nishio
13
面白い本だった。初刊は85年だというが全く古びない。古代から室町時代が中心で、大陸からの影響を中心に読み解く。出雲が新羅とつながっていた第3の航路であったとかホントかいなという話も面白く読めた。印象に残ったのは、吉備の国と、備前福岡、いずれも岡山県の話。岡山がこれほど重要な場所であることを初めて知った。今度行く時に見方が変わるだろう。2016/06/30
時代
12
司馬さんと林家辰三郎氏の対談。古代日本を話の中心に大和と出雲、韓国、中国、宗教、数寄屋文化、金と銀と、などなど話題は多方面にわたる。肩肘張らない軽快なやり取りが心地良い。とても面白く読ませて頂いた◎2020/03/31
非日常口
8
◆蘇我馬子は実は外交インテリジェンスの天才だったのかもしれない。高句麗から情報を得ていた彼は戦争をしたがる勢力にのせられた崇峻天皇(当時は大王の一人扱いだったらしい)を暗殺することで内政重視の路線を強行、それは大化の改新以降も下地となる平和思想だったそうだ。◆琵琶湖は日本のオンパロース。船乗りの実力も屈指で秀吉が朝鮮征伐に行く際もここから人手を調達。◆自分の土地というリアリズムの芽生えと墾田永年私財法や源平の関係。地政学的にも、時系列的にも、人口動態や文化萌芽、様々な歴史の視点を林屋・司馬は提示する。2013/06/22
桑畑みの吉
4
国民的作家の司馬遼太郎氏と歴史学者の林屋辰三郎氏の対談集。計8回いずれの対談も1972~1980年に行われた。お二人の話は歴史の重箱の隅をつつくマニアックな内容ではなく非常に読みやすかった。全体的には東アジアを絡めた日本の確立、関西・関東といった都市の発展、こころの底流として宗教の話題が多めだった。中でも足利義政に始まる金銀の話が印象に残った。政治家としては無能だったが、結果として東山文化を生み出した。それは銀の文化であったが、以降は金の文化が優勢。その金の流出が徳川幕府の命取りになったそうである。2025/05/14
-
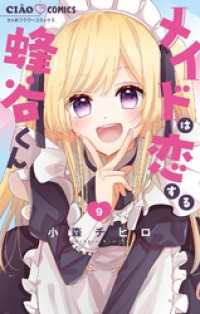
- 電子書籍
- メイドは恋する蜂谷くん【マイクロ】(9…
-
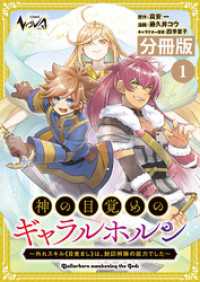
- 電子書籍
- 神の目覚めのギャラルホルン~外れスキル…
-

- 電子書籍
- AUTOSPORT No.1555
-

- 電子書籍
- 異世界キャバクラ 第2話【単話版】 コ…
-
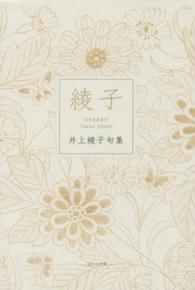
- 和書
- 綾子 - 井上綾子句集




