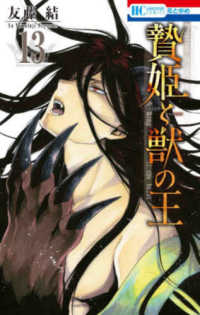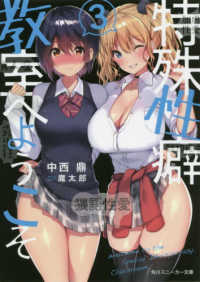内容説明
「男と女の、社会的な同質化現象はさけがたい」――今や当たり前にも思えることを六十年前に民族学者の立場から徹底的に論じた梅棹忠夫。発表するや賛否両論の大反響を巻き起こした「妻無用論」「母という名のきり札」を含む慧眼の書。有賀薫氏、酒井順子氏、花田菜々子氏推薦。
〈解説〉上野千鶴子
【目次】
まえがき
女と文明
アフガニスタンの女性たち
タイの女性たち
家庭の合理化
妻無用論
母という名のきり札
家事整理の技術について――家事整理学原論Ⅰ
すてるモノとすてられないモノ――家事整理学原論Ⅱ
あたらしい存在理由をもとめて
女と新文明
情報産業社会と女性
『女と文明』――追記
解説 「妻無用論」から半世紀をへて 上野千鶴子
-

- 電子書籍
- 清麿大鑑 普及版
-
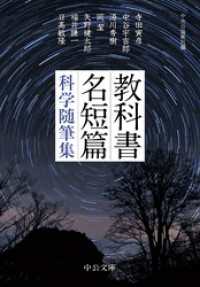
- 電子書籍
- 教科書名短篇 科学随筆集 中公文庫