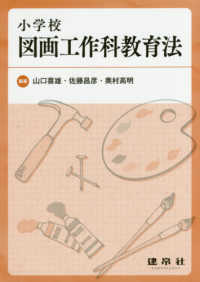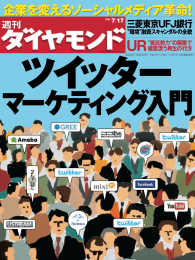内容説明
インドを中?に世界を旅してきたジャーナリストが、?他の旅の記憶をていねいに辿りながら「?が旅に出る理由」を重層的に考察するエッセイ。
なぜ人は何度でも、何歳になろうと旅に出るべきなのか。
それは旅こそが私たちにとって最?のセラピーであり、?分を育む?為にほかならないからだ。
旅好きも、旅が遠くなった?も必読の滋味あふれる旅論。
【スウェーデン発、欧州ベストセラー!】
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mura_ユル活動
131
私は旅行が好きだ。人付き合いがうまくなく、学生のころからは建物を見に行ったり、山に登ることをしていた。読友さんが読まれていた本、地理文化には詳しくないが読むことできた。スウェーデン人ジャーナリスト、アンデション著。巻末に「読めば放浪したくなる旅行記22点」を掲げる。思い出、憧れ、映画や小説の舞台、駅や港・島。自然界と都会。旅は心を健康に保ち、セラピー要素がありトラベラーズ・ハイも誘発する。15章の「人は旅で本当にかわるのか」が特に興味を引いた。物事を高く評価するようになる。→続く2020/09/13
あすなろ@no book, no life.
83
人は何故旅をするのか? 僕は著者の様な旅はしていないのかもしれない。しかし、特に社会人となってから出張や出張に併せた旅なら1年の何分の1を費やしているのか。交通手段・食事・宿・景色・気候等から自らに得るインフォメーション量はもの凄い数であろう。何故なら、己は異邦人なのだから。筆者は様々な旅の効用を書き連ねる。自身の体感や経験と照らし合わせられる。僕は未知の土地から自分への養分を得た上で、全く未知のその土地を少しずつ理解していくというその過程が好きだし、己が試される感が好きだ。そういう思索に耽ることが出来る2020/10/04
獺祭魚の食客@鯨鯢
56
読書家で知られる出口治明さんは「人生を豊かにしてくれる3本柱」として「人・本・旅」を挙げている。三者は相互に連関している。 私の場合の順番は本・旅・人である。スパイスとして知的好奇心。 この何年か経験する旅とは名作の舞台への巡礼である。古事記や万葉集に現れる聖地には神社が存在し、名山にもご神体を象徴する社がある。旅先で出逢う人びとは、誰もが暖かい。 本書は外国人が書いたものであるが、巧みな筆致で日本人の私にも非日常的な空間での「あるある」心理が浮き彫りにされる。(翻訳が良いからかもしれない) 2021/11/23
獺祭魚の食客@鯨鯢
53
出口治明氏は人生を豊かにしてくれる3本柱として「人・本・旅」を挙げています。それは気の置けない友との会話、古典の味読、なりゆきの聖地巡礼旅。 旅を意味する英単語はtravel、trip、journeyとありますが、外国は物見遊山的が多いようです。 日本人は求道的travel(「苦しみ」が語源)が好きです。聖なるものへの憧憬意識が高い。 Go To トラベルは決してコロナ前への回帰ではない。第一波の時のパチンコ事業者のように、意味なく割りを食わせることがないように配慮すべきである。 2020/11/23
seacalf
49
首都圏から脱出して山奥の雪舞う温泉地に引きこもり。こたつにもぐり込みながら、読む。パックパッカーだった作者の実体験と旅に関する様々な考察。全人類の二割が持っているという旅の遺伝子DRD4ー7Rの存在を初めて知る。わくわくする記述もちらほらあるが、全体的に少し冗長気味。公平であろうとしてるが、やや尊大。旅エッセイを読む時によく感じる焦がれるような強烈な旅への飢えは感じられず。囲炉裏を前にした食事や雪見露天、そして帰り際に『電車の中で食べて』と女将さんが渡してくれたみかん2個の方が自分には旅の効用があった。2020/02/25