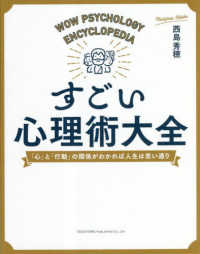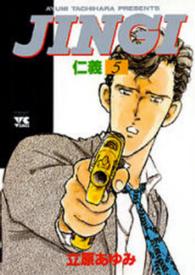内容説明
「ウェルビーイング(Wellbeing)」とは、身体的にも、精神的にも、そして社会的にも「よい状態」のこと。心身ともに満たされた状態であることを指す言葉です。情報技術が私たちの暮らしを便利にする一方で、利用者の心の状態への負の影響も指摘されている現在、ウェルビーイングに対する注目が高まっています。
本書は、ウェルビーイングとは何なのか、そしてそれをどのようにつくりあうことができるのかについて解説した書籍です。わかりあえなさのヴェールに包まれた他者同士が、根源的な関係性を築き上げ、共に生きていくための思想、実践、技術を照らし出します。
ユーザーに愛されるプロダクトやサービスの設計を目指すデザイナー、エンジニア、ビジネスパーソン、また、組織環境を良くしたい人事・総務担当者などにおすすめの一冊です。
「わたし」のウェルビーイングから、「わたしたちの」ウェルビーイングへ。「個でありながら共」という日本的なウェルビーイングのあり方を探求します。
論考:
伊藤亜紗/生貝直人/石川善樹/岡田美智男/小澤いぶき/神居文彰/木村大治/小林 茂/田中浩也/出口康夫/水野 祐/安田 登/山口揚平/吉田成朗/ラファエル・カルヴォ
目次
はじめに
Introduction|「わたしのウェルビーイング」から始めよう
1300人の大学生が考えた「わたしのウェルビーイング」
「ウェルビーイング」を考えるために
Part 1 What is Wellbeing?|ウェルビーイングとは何か?
1.0 Overview|ウェルビーイングの見取り図
1.1 Individual Wellbeing|「わたし」のウェルビーイング
1.2 Collective Wellbeing|「わたしたち」のウェルビーイング
1.3 Social Wellbeing|コミュニティと公共のウェルビーイング
1.4 Internet Wellbeing|インターネットのウェルビーイング
Part 2 Wellbeing in Practice|ウェルビーイングに向けたさまざまな実践
2.0 Intoroduction|テクノロジーから「自律」するために ラファエル・カルヴォ
2.1 Technology|情報技術とウェルビーイング
2.1.1 感情へのアプローチが行動を変える 吉田成朗
2.1.2 〈弱いロボット〉の可能性 岡田美智男
2.1.3 「生きるための欲求」を引き出すデジタルファブリケーション 田中浩也
2.1.4 IoTとFabと福祉 小林 茂
2.2 Connection|つながりとウェルビーイング
2.2.1 予防から予備へ:「パーソンセンタード」な冒険のために 伊藤亜紗
2.2.2 「沈黙」と「すり合わせ」の可能性 木村大治
2.2.3 孤立を防ぎ、つながりを育む 小澤いぶき
2.3 Society|社会制度とウェルビーイング
2.3.1 お金から食卓へ:貨幣とつながりの現在地 山口揚平
2.3.2 ウェルビーイングと法のデザイン 水野 祐
2.3.3 本人による自己の個人データの活用 生貝直人
2.4 Japan|日本とウェルビーイング
2.4.1 「日本的ウェルビーイング」を理解するために 石川善樹
2.4.2 「もたない」ことの可能性:和と能から「日本的」を考える 安田 登
2.4.3 祈りとつながり、文化財と場所 神居文彰
2.4.4 「われわれとしての自己」とウェルビーイング 出口康夫
Part 3 Wellbeing Workshop|ウェルビーイングのためのワークショップ
3.1 なぜ「ワークショップ」なのか?
3.2 ウェルビーイングワークショップの流れと各ワーク
3.3 「頭」と「心」と「手」を結ぶ
座談会:「わたしたち」のウェルビーイングに向けたプロジェクト
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アキ
けんとまん1007
kana
Shohei I
izw
-
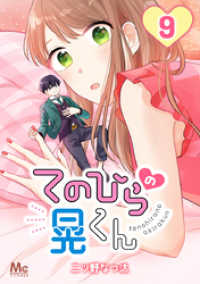
- 電子書籍
- てのひらの晃くん 9 マーガレットコミ…
-

- 和書
- シンハラ語会話練習帳