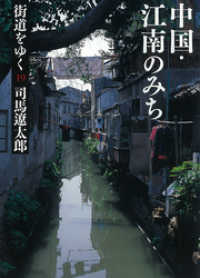内容説明
平安京=京都ではない!
清水寺、知恩院、三十三間堂、祇園、東山、鴨川……いずれも平安京の外だった。
では、今の「京都」の原型をつくったのは一体誰なのか。
壮絶な権力闘争と土地開発の知られざる物語を気鋭の歴史学者が読み解く。
【これを読めば「京都」通になれる】
●武装した強盗集団に狙われ続けた平安京
●平安京には寺を作ってはいけないルールがあった
●廷臣の邸宅を次々と移り住む天皇
●貴族も庶民も楽しんだ「晒し首」パレード
●勝手に戦争して顰蹙を買った源氏
●都のど真ん中で起こった殺し合い「保元の乱と平治の乱」
●京都駅周辺を開発したのは平家だった