内容説明
■第29回山本七平賞・奨励賞 受賞
■紀伊國屋じんぶん大賞2021(紀伊國屋書店 主催) 第5位 入賞
■読者が選ぶビジネス書グランプリ2021(グロービス経営大学院+flier 主催)リベラルアーツ部門 第4位 入賞
これが、ニュー・ノーマル時代を切り拓く哲学書。
「ずっとじぶんでも考えていたことが、別の光を当ててもらったような気がして、読んでいて興奮しました」
――糸井重里(株式会社ほぼ日 代表)
「わたしはすでに受け取っていたんだ。読むと次にパスをつなげたくなる本」
――伊藤亜紗(東京工業大学准教授・美学者)
「贈与を受け取ったから、私は家族の物語を書きはじめました」
――岸田奈美(作家『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』)
「人間の『こころ』の力動の機微をとらえる近内さんのセンスには肌の温かさと機械の精緻さがある」
――茂木健一郎(脳科学者)
「コロナ後の経済は『贈与』を軸に駆動します。必読でしょう」
――山口周(独立研究者)
2020年最有望の哲学者、「希望」のデビュー作
この資本主義社会で「お金で買えないもの=贈与」が果たしている役割とは何か?
「人間」と「社会」の意外な本質を、みずみずしく平易な文体で驚くほどクリアに説き起こす。
ビジネスパーソンから学生まで、
見通しが立たない現代を生き抜くための、発見と知的興奮に満ちた「新しい哲学」の誕生!
「一見当たり前に存在しているこの『世界』の成り立ちを、『贈与』や『言語』、『常識」の成り立ちを通して説き起こした鮮烈なデビュー作。
人間の『こころ』の力動の機微をとらえる近内さんのセンスには肌の温かさと機械の精緻さがある。
ウィトゲンシュタインと小松左京の本書を通しての出会いは思考世界における一つの『事件』。
社会の見え方を一変させ、前向きに生きるために、この本を処方せよ!」
―――茂木健一郎
目次
第1章 What Money Cant Buy――「お金で買えないもの」の正体
第2章 ギブ&テイクの限界点
第3章 贈与が「呪い」になるとき
第4章 サンタクロースの正体
第5章 僕らは言語ゲームを生きている
第6章 「常識を疑え」を疑え
第7章 世界と出会い直すための「逸脱的思考」
第8章 アンサング・ヒーローが支える日常
第9章 贈与のメッセンジャー
目次
目次
第1章 What Money Cant Buy――「お金で買えないもの」の正体
第2章 ギブ&テイクの限界点
第3章 贈与が「呪い」になるとき
第4章 サンタクロースの正体
第5章 僕らは言語ゲームを生きている
第6章 「常識を疑え」を疑え
第7章 世界と出会い直すための「逸脱的思考」
第8章 アンサング・ヒーローが支える日常
第9章 贈与のメッセンジャー
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
mura_ユル活動
trazom
なかしー
ムーミン
小太郎
-

- 電子書籍
- 犬神 フルカラー改訂版 2巻 LINE…
-
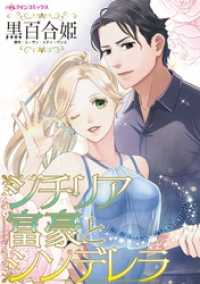
- 電子書籍
- シチリア富豪とシンデレラ ハーレクイン…
-
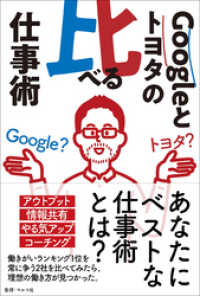
- 電子書籍
- Googleとトヨタの比べる仕事術
-
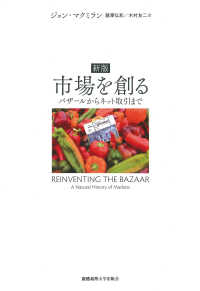
- 電子書籍
- 新版 市場を創る - バザールからネッ…
-

- 電子書籍
- らずべりぃMix(1) まんがフリーク




