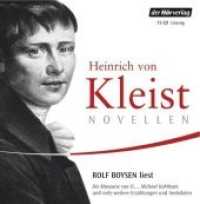- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
3Mのポストイット、Gメール、ピクサーアニメ、
0-1を生むアート思考とは、ひらめきが宿る「余白」を創出することである――
MBA(経営学修士)とMFA(美術学修士)をもつアートシンキングの第一人者が贈る、
いまもっとも読んでおきたいビジネス書の1冊。
『「アート的な思考をビジネスに盛り込む」ための具体的なヒントが、ぎっしりと詰まっています』――まえがき 山口周氏
山崎直子氏(宇宙飛行士)竹林一氏(オムロン)臼井重雄氏(パナソニック)ほか日本発の7事例も収録!
アートシンキングとは
▼ そもそも「これは実現可能か?」という問いを発すること
▼ 今いるA地点から、未知のB地点を作り出すこと
▼ 専門分野にとどまらず、広角レンズで世の中を見ること
▼ 失敗しても大丈夫と自分に「失敗許可証」を与えること
▼ 不安や孤独の中においても自分自身を心から信頼すること
▼ マネジャーは「案内人」「同志」「プロデューサー」になること
▼ 創造的スペース=「余白」を自分の中につくること
目次
【目次より】
まえがき 山口 周
序章 命を救うこと vs 命を救う価値のあるものにすること
美術学修士号(MFA)は、新たな経営学修士号(MBA)である
アートとは何か
未知のB地点のある世界
飛行機を離陸させる
ピンと鉛筆の話
アートとデザインとクリエイティビティ
第一章 広角レンズで見る
オブジェクトと環境
海を沸騰させる
エネルギーと時間を管理する
図と地
エリヤの椅子
スタジオタイム
〈20%ルール〉が生み出したもの
創造性のカテゴリー
未完成にこそ価値がある
天才アーティストという神話
無駄なものは何もない
何もしていないという不安
知らないことの恩恵
日本の牽引者事例1 パナソニック株式会社 デザイン本部長 臼井重雄
第二章 草むらの中で
草むらのための三つのツール
創造的プロセス vs 創造的成果
判断すること vs 把握すること
イーゼルとひじ掛け椅子
新しい作品を守る
猶予期間を設ける
ベースキャンプ vs エベレスト
生まれたての会社と成熟した会社
逆行分析(リバースエンジニアリング)
意識を向ける
マインドフルネスの効果
気づきを得る
日本の牽引者事例2 慶應義塾大学 環境情報学部 教授 神成淳司
第三章 灯台の光が照らす先へ
地図なしで進む
クラーク・ケントの日常
仲間との絆
最初の四分間
SMARTゴールからMDQへ
暗号に魅せられて
プライバシーを守る
求められた場所で咲く
先行者に厳しい世界
新たな挑戦を見いだせないときに
日本の牽引者事例3 宇宙飛行士 山崎直子
第四章 ボートを作る
『包まれたライヒスターク』vs ツイッター
ポートフォリオ思考
自己投資
カウチとスローピロー
成長
市場シェアマトリクス
分割所有権
絵画のアップサイドリスク
グレーゾーンの所有権
芸術か、それとも盗用か?
デジタルコンテンツの所有権の特徴
日本の牽引者事例4 京都造形芸術大学 教授 小笠原治
第五章 創造を導く
ほどよいマネジャー
導師(グル)と案内人(ガイド)
同志関係
プロデューサー
モノを買える環境を創造する
改訂版スクラム
マイルストーンを設定する
創造的プロセスをマネジメントするときの落とし穴
パフォーマンスを計測し、採用に活かす
プロジェクトを完了させる
日本の牽引者事例5 オムロン株式会社 イノベーション推進本部 インキュベーションセンタ長 竹林 一
第六章 家を建てる
眼鏡はなぜ高いのか?
物質的リソースの活用
固定費と変動費――ウェッジウッドの例
「不完全」と「もしも」のコスト
部屋の中のモノからビジネスモデルを想像する
ミッドフィルダー企業
潜望鏡で観察する
日本の牽引者事例6 一般社団法人 アート東京 代表理事 來住尚彦
第七章 全体を見渡す
ジンジャーブレッドマン vs ウィトルウィウス的人体図
ゼネラリストのすすめ
問いを発する力
帰ってきたアートとサイエンス
スラッシュキャリア
自分のメタファーをデザインする
ユニバーサルコンセント
アダム・スミスはアーティストだった
現代社会の抱える問題
クロスタウンの船出のとき
日本の牽引者事例7 株式会社スマイルズ 代表取締役社長 遠山正道
原注
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえぽん
しゅー
yyhhyy
nks
koy_ou
-

- 和書
- 17の鍵 創元推理文庫