内容説明
「人間の本性とはなんであるか、政治体とはなんであるか、また、いわゆる法とはなんであるか」。1640年に発表された最初の政治理論で、ホッブズはこれらの問いに答える。人間本性の分析を通して描き出される、自然状態=戦争状態。そこから脱する政治体として、選ばれるべきものは何か――。大著『リヴァイアサン』へと発展する議論の核心は、本書のうちに用意されているといってよい。イングランドが政治的混乱に見舞われるなか、ホッブズの願いは、自らの学説によって人々に平和への指針を示すことにあった。「ホッブズ哲学の最良の展開の一つ」と評される作品を、達意の訳文と充実した訳注でおくる。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かわうそ
45
教科書的な説明ではホッブズは抵抗権を否定しているのだと説明される。それは正解でもあり間違いでもあることが本書で確認できた。抵抗権を主権者に対する反乱の意味で捉えるなら抵抗権を否定したと言われても間違いではない。ただし、人民が集会の場を持ち、主権が人民にある場合は統治者を罷免できるのだ。なぜなら統治者は主権者ではなくて臣民だからである。このように統治者が臣民であるという想定では抵抗権に似た何かが存在することになる。そこを誤解するとホッブズが改革を否定したかのように受け取ってしまうことになると思う 2024/05/30
かわうそ
35
題名のインパクトと知名度ゆえに『リヴァイアサン』の方が評価されがちだが、『法の原理』の方が冗長な感じもなくホッブズの主張が驚くほど見事にまとまっており個人的にはこちらの方が好み。 『しかし、それは(自然の法の場合のように)各個人の私的な理性ではなく、将軍の理性が要求するところにしたがうのである。』このたった1文章で1人の理性が法になる場合は主権的権力が背景にあること、各人の互いの理性が法になる場合は自然法であることを示していることは見事という他ない。 読んでいてハッとさせられる部分が多い。2024/11/09
1.3manen
30
1640年初出。ホッブズ52歳のときの作品(訳者解説444頁)。 人生をレースに例えている箇所は、まとまりとして詩歌のようであるのは不思議だ(101-3頁)。努力することは、欲求である。怠けることは、肉欲にふけることである。他人が遅れていると考えることは、栄誉である。他人が先にいると考えることは、謙虚である。振り返って地歩を失うことは、自惚れである。抑えられることは、憎悪である。引き返すことは、後悔である。一息することは、希望である。疲れはてることは、失望である。2020/02/02
ポルターガイスト
4
自然権・自然法思想というのがどういうものかの感触が得られたのがいちばんの収穫だった。教科書には「人間が生まれながらに持っている権利が自然権」などと書かれているが全く納得できなかった。この本ではどちらかと言うと「人為的に作られた過去の法の伝統に束縛されないために一から法制度を考えるための方法」という感じでずっと腑に落ちた。一貫して人間性に対して悲観的で,バークリやヒュームなどを読んでいる気分に近かったが,やはりホッブズは一般的に政治学者として扱われるだけあって,前半の人間本性についての議論は粗雑に感じた。2022/06/04
Fumoh
3
1640年のホッブズの政治論で、あの『リヴァイアサン』よりも前の論考だが、『リヴァイアサン』で将来書かれる、ホッブズの政治哲学の本質はここでも表れている。それが「主権の統一が絶対に必要」であるということと、「理性に基づいて主権に服従するべきだ」ということ。イングランドとスコットランド、アイルランドという三つの国の思惑が交錯していたイギリスにおいて、ホッブズが「主権の統一」を叫んだのは、まさに当然であった。ホッブズはペンを用いてイギリス政治に貢献しようと考えていたようだ。そのため実際的な問題に関心が強く、2024/12/19
-

- 電子書籍
- FLASHデジタル写真集 ミンミコ 甘…
-
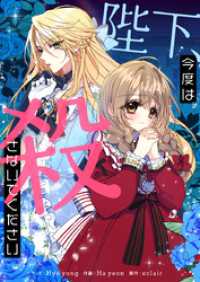
- 電子書籍
- 陛下、今度は殺さないでください【タテヨ…







