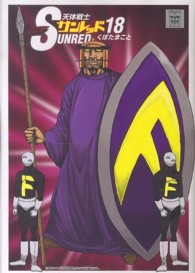内容説明
考現学は未来を考える立場だ──。ジャンパーを着て日本中を歩き回り、民家、服装、都市文化、世相など現代風俗研究に前人未到の足跡を遺した第一人者が綴る生活者の視線。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
30
路上観察学にハマったとき(必死にトマソン探してました)に知った著者。バラック装飾社の活動はすごいカッコイイと思ったし、気が狂ったような観察記録も楽しかったが、その文章をまとめて読むのは初めて。大正末期から高度成長期まで50年にわたって、表現や観察の姿勢から日常まで広く集めている。◇柳田国男の弟子でありつつ離れて独自の世界を作っているのは宮本常一と同じだが、この人はよりモノへの執着が凄い。集めて位置づけて整理して…。どんなモノに対しても意味づけできる力はどの文章からも感じられて、何だかやはりとても楽しい。2019/11/28
ジャズクラ本
12
○今和次郎氏について何の知見もないが、本書を読む限りとても気さくな方のように見受けられた。考現学という民俗学の一カテゴリーを立ち上げられた方の様だが、親しみやすい文章で肩肘はらずに読むことができた。身なりは冠婚葬祭から高松宮や米国大使との会談にいたるまで一貫してジャンパーにズックという出で立ちで通されたとある。晩年(1967年)に出席された結婚式で、「50年後には結婚式も私のようなスタイルになる」と予言されているが、どうもまだそうはなっていないようである。否、最近の人前婚はこれにあたるのかな。。うーん。。2019/10/24
かわかみ
8
建築家であり、考現学を提唱した著者のエッセイを集めた本で味わいがある文章だった。著者は民俗学を歴史学を補完する学問とし、現今の社会を解明する社会学を補完する学問として考現学を企図したようだ。だが、柳田國男からは君のしようとしていることも民俗学なのだと言われ破門された。たしかに柳田の「明治大正史世相篇」は社会学でもあると加藤秀俊氏は述べていた。今日、考現学の観察的好事家的側面は「路上観察学」?が継承したが、計量的科学的側面は雲散霧消したのではなく、マーケティング論に継承されているようにも見える。2025/05/08
Sakurai Daisuke
4
考現学という学問を通して世間を観察すると日常も面白いものなのではないかと思えてくる。 今の時代から当時を見てみると考現学で調べられたことが時代を読みとく資料として、現代においてもはっきりと再現されていく素晴らしさを感じた。 考現学を発案した今和次郎に感謝したい2019/12/09
夏みかん
3
学者さんとしては珍しく目線が低いというか身近に感じられる方だったんだろうなと思った。街中の身近なモノに心惹かれる人だし、その心も街中の普通の人と共にあったんじゃないかな。常にジャンパーにズックというのは逆に徹底しすぎてて頑固さを感じたけどね。残念ながら結婚式や葬式にジャンパー姿は今でも厳しいなあ。。2019/11/28