内容説明
日本という国はひとつの民族が、ひとつの言語を使い、ひとつの国家を形成して、長い長い歴史を持っていると習います。けれどそれは明治時代から戦前までの教育の名残です。では、どのように今の日本になったのか? 日本史を通して学びましょう。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
94
日本という国、日本人という人々はどんなメンタリティを持っているのか、歴史を辿り見通す。気候温暖で、まずまず”食っていける”。いわゆる「草食系」で争いを好まず、有能なリーダーは不要。白村江の敗戦、ペリー来航など「外圧」でしか変わらない。社会が安定すると世襲が幅を利かす。地位より人、才能より血。日本人は国会議員の世襲にわりと寛容。官僚は大嫌い。「世襲」の長所は争いがほぼ起きないこと。官僚のように「才能」を頼りに出世を目指すと熾烈な競争が起きる。草食系は争いを好まず競争するような人たちも嫌いと、皮肉を飛ばす。2020/02/22
へくとぱすかる
69
この本で教えてもらったこと。日本の歴史・地理を考えるとき、無意識に、現在の姿を過去に投影していないかを、警戒すべきだろう、という点。和同開珎に始まる銭貨が、列島各地に流通していたように想像するのも幻想だ。ということは、平清盛は宋銭により貨幣経済を復活させたのではなく、本当の意味での貨幣経済のパイオニアだったのだろう。本書全体を通じて、日本の歴史を貫く本質を追求する論は、実にスリリング。巻末第五章がとくに気味よく、腑に落ちる。また、赤穂事件の原因を「パワハラ」と表現するのは、さすが現代的。わかりやすい。2021/09/01
金吾
22
どちらが先なのかはわかりませんが、他の本でも読んだ著者の主張が多かったです。その分読みやすいとも思いました。日本自体が草食系という話は風土は性質を作ると思っている私にとって理解しやすい説でした。2024/06/11
アナーキー靴下
21
日本史を繋ぎ合わせて今の日本に至る道筋を見せる、みたいな本を想像していたが、日本人気質と照らし合わせながら日本史を紐解く、といった風の、気軽に楽しめる読み物。現代人からの視点で見ることで、日本史がより身近に感じられる。最終章「日本史を学ぶ意義」はそれまでの章とは趣の異なる、著者のメッセージだが、そこまで読み進めたからこそ著者の言いたいことがすっと入ってくる。因果関係を見出だすことに歴史を学ぶ価値があると言うのは尤もで、歴史はすでに結果が得られた社会実験だと考えれば、無駄にするのはもったいないことだ。2020/09/24
新父帰る
11
2020年2月刊。古本屋で購入。本郷先生のは今まで何冊か読んだ。本棚へ思わず手が伸びた。日本の成り立ちを分り易く説明。江戸の無血開城の話。西郷は最初総攻撃するつもりが、静岡で気が変わったが、著者はその訳が分からないとする。しかし、他の書では山岡鉄舟が西郷を説得したとあるが?外圧しか変わらないニッポンは島国日本、平和を長く享受した日本であるから納得。世襲の話、昔から今日まで変わらないのも納得。最後に日本の歴史と宗教は特に面白かった。著者は本当は寺の住職になりたかったようだ。特に宗教の説明が分かっり易い。2022/11/08
-
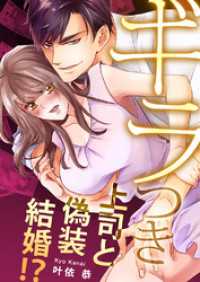
- 電子書籍
- ギラつき上司と偽装結婚!?【全年齢版・…
-
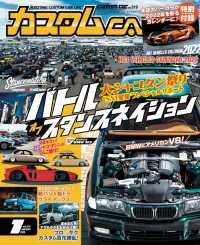
- 電子書籍
- カスタムCAR 2022年1月号 vo…




