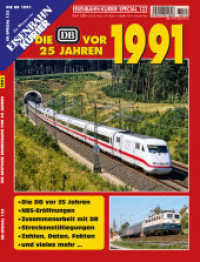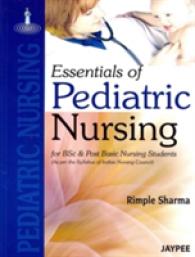- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
理不尽な上下関係や努力信仰が幅をきかせ、抑圧的な組織の論理がまかり通る日本社会――。われわれの多くに刷り込まれたこのような常識や行動様式はどこから来るのでしょうか。江戸時代以降、中国の古典『論語』は、日本人の無意識の価値観のもととなってきました。本書では、『論語』や儒教のものの考え方を丁寧によみとき、さまざまな国際比較研究の知見と照らし合わせることで、わたしたち自身を無自覚のうちに縛るものの正体を解き明かします。己を知り、より自由に生きるための、現代人必須の教養書です。
目次
I 『論語』の価値観『論語』と孔子の教えについて
江戸時代の秩序と『論語』
近代日本の教育と産業界
II 学校ではどうなっているのか
結果が出ないのは努力不足
集団指導
気持ち主義
III 会社ではどうなっているのか
旗が立っていない会社と個人
秩序維持と進歩と
IV 『論語』的価値観をうまく扱うために
日本人はホンネのはけ口を求めている
手段としての「論語と算盤」
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
だい
15
論語のエキスパート守屋淳さんのエッセイ教本です。日本人らしさとは?また日本人らしさの根源は?…という漠然とした疑問を紐解いていきます。論語の価値観から始まり学校、会社での日本人の隠れた心理など興味深い内容でした。欧米の学校と日本の学校の違いが根本のような印象を受けました。 儒教が広まっている日本、韓国、中国は道徳の授業があるのに対し欧米では無いという事に驚きました。事勿れ主義に過剰に反応し、トラブルが起きるとまずは謝罪する日本人…風習とは恐ろしいものですね。 2023/02/18
makio37
14
こうして読むと、自分の中に論語的価値観が染みついているのがよく分かる。学校では弱点の少ない君子型の成績を目指し、されて嫌なことを他人にしない「恕」の刷り込みから悪しき行動はしないが積極的に良いこともしない。会社ではルールや法は上から与えられるものとし、分をわきまえ、ホンネとタテマエを使い分けるのは当然と考える…。渋沢栄一が"欧米列強から植民地にされない日本を作る"という目的のための手段として用いた論語の価値観自体を、目的化してしまった社会と自分。今回、これらを意識化できただけでも有意義であった。2020/03/29
sakanarui2
7
日本の家庭や学校、企業、社会全体に関して、「なんでこんなことになってるのか」知りたいと思って。この本は、儒教がいつどのように日本に入ってきて、時の権力によっていかに都合よく解釈され、統治に生かされてきたか、それによって今日の社会にどのような影響を及ぼしているかについて(主に悪い影響を中心に)書かれている。面白い。 どうにも理不尽だと思っていた日々の出来事やどうにも話が噛み合わない相手の、背景にある思考の枠組みを知ることで、今後の対処のヒントになるかもしれない。2023/07/16
たくみくた
7
56冊目。『孫子』にある「彼を知り、己を知れば百戦して殆うからず」というように、日本人の価値観に深く根付いている『論語』=儒教についての理解が深まる本。① 孔子が生きた時代は戦乱の世の中。ゆえに彼の思想の前提には「戦乱状況だからこそ、求められた平和な秩序の構築や維持」という側面がある。(マキャベリの『君主論』がそのまま現代で使えないのと同じ。)② 「己の欲せざるところ、人に施すことなかれ」=「他人様に迷惑をかけちゃだめですよ」と多くの人が言われて育っている。「己の欲するところを人に施せ」とは似て非なるもの2020/10/17
Masatoshi Oyu
6
日本人が無意識に従っている「長幼の序」、「性善説」、「家族主義」、「精神主義」などの価値観の淵源を(徳川封建体制を強化するためのイデオロギーとして変形された)儒教に求める。「君子」を理想として君臣の秩序を絶対視し、「政は正」と考え、「本質より大局・関係性」を重視する儒教的価値観と、「神(法)の下の平等」を理想とし、「法による正義」の実現や「大局より本質」を重視する西洋の価値観との間には大きな溝がある。2020/03/23