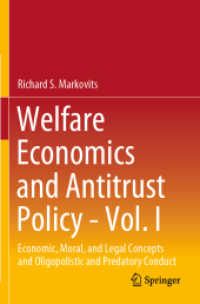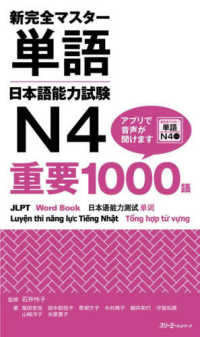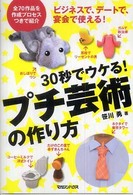内容説明
古代ローマ史の泰斗による、古代地中海世界の歴史。講談社現代新書で好評を博したシリーズ「新書西洋史」全8冊のうちの第2巻として刊行されたが、単なる概説書にとどまらず、古代史への新しく、大きな視座を提供した、定評ある意欲作。
本書は、ほぼ2000年にわたるギリシア・ローマの歴史を扱うが、「ギリシア」と「ローマ」という二つの歴史を扱っているのではない。「ギリシア・ローマ」という一つの世界の一貫した歴史として追及する。
現在の西半球の主要な歴史の担い手とその文化は、地中海世界を母胎として生み出されたものであった。ラテン的・ゲルマン的世界、ギリシア的・スラブ的世界、オリエント的・アラブ的世界は、地中海世界の崩壊の中から生み出された第二次的世界であり、キリスト教的東西ヨーロッパ文明、イスラム的アジア文明は、地中海世界の転生の中から生まれたものだった。地中海世界は、それらすべてのものの出発点であり、母胎であり、故郷なのである。巻末解説を、東大名誉教授・本村凌二氏が執筆。〔原本:『新書西洋史2 地中海世界――ギリシアとローマ』講談社現代新書、1973年〕
目次
まえがき
第一章 地中海世界に何を問うか
第二章 東地中海と古典ギリシア
第三章 ギリシア=ポリスの成立
第四章 ポリスの発展と衰退
第五章 ローマの発展
第六章 ローマ帝国の支配構造
第七章 ローマ帝国の支配のイデオロギー
第八章 ローマ帝国の衰亡
年表
解説(本村凌二)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
70
ギリシア以前ミケーネ文明から、ギリシアを経てローマ衰亡までを通史として描いた一冊。中心となっているテーマは、共通するような政治形態を採っているにも関わらず何故ギリシアは衰えローマは発展したのか。そのため頁数の割には扱う範囲が広いように思えたが、歴史と社会制度のみに焦点を当てている為に私のような初心者にも非常に読みやすくなっている。その流れとして漠然とポリスという単語を知っているくらいな身としては、各文明がどのように時代に合わせて変化していったか興味深く読めた。何より通史として楽しめるのも大きいなあ。2020/06/19
まえぞう
24
本村先生の大作でも紹介されてたので手にしました。原作は50年も前の著書ですが、ギリシャ、ローマの歴史が外観できます。両者の発展の違いは市民権を限定したのか解放したのかにあるようです。2025/12/28
TS10
16
共同体の分解と統合の観点から書かれた、ローマ史碩学によるギリシア・ローマ史の通史。オリエントとは異なって灌漑を用いない農業は、平等の原理に基づくギリシア世界を形成したが、共同体成員の資格を排外的に制限したことは、流通経済の発達によりもたらされた格差拡大とそれに伴う共同体の分解を避けられないものとした。一方、ローマにおいては、征服した共同体の支配層と植民都市とをローマ市民権を媒介にローマ共同体に統合し、帝国を形成した。やがて、「内乱の一世紀」を経て、皇帝と官僚及び軍隊にのみ支配層は制限され、アントニヌス勅令2025/08/02
mahiro
15
ギリシァ文明からローマ帝国の興亡までダイジェスト的に流した感じだが、ローマが巨大帝国になり維持のため制度に矛盾が生じ、外圧内憂により分裂崩壊して後、ヨーロッパやアラブ、スラブ文明世界の苗床になる過程がダイジェスト故にとてもわかりやすく読めると思う。2020/03/30
あんどう れおん
8
「ギリシャとローマ」の併記ではなく「ギリシャ・ローマ」の連続した叙述を目指す意欲作。効率よく概観するためか、定義の不明な固有名詞も散見されます。一流の専門家による書物であることはよく分かりましたが、著者自らが「まえがき」で推奨した気楽な読み方ができるかどうかは疑問だと感じました。2020/10/02