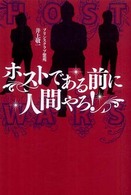内容説明
鎌倉時代は「いい国つくろう」の1192年に始まる、という時代区分はもはや主流ではない。日本史の研究は日々蓄積され、塗り替えられている。今注目されている日本史の論点は何か、どこまで解明されたのか。「邪馬台国はどこにあったか」「応仁の乱は画期なのか」「江戸時代は「鎖国」だったのか」「明治維新は革命なのか」「田中角栄は名宰相か」など、古代・中世・近世・近代・現代の29の謎に豪華執筆陣が迫る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
107
古代から現代まで、学校で学んだ日本史の常識を片端から引っくり返してくれる。邪馬台国は実は「倭国連合」だったとか、墾田永世私財法は律令制度を強化するものと言われても「?」だ。江戸時代に大きな政府と小さな政府の交替があったとは思いがけぬ視点だし、庶民にまで行き渡った教育から江戸から明治への連続性と官僚主義の誕生を例証されては頷くしかない。うっかり歴史について知ったかぶりをしたら大恥をかきそうで、どの分野でも最先端の研究成果を把握する必要を痛感させられる。もっとも大半の人は、そんなことを考えてもいないだろうが。2021/02/15
佐島楓
66
近世から現代に至る政治機構の共通項という新たな視点が得られたのは面白かった。巻末の「日本史をつかむための百冊」などを参考にして、自分の考えを確立していきたい。2018/09/21
もりやまたけよし
64
古代から学会の論点になっている部分を総括的に取り扱っている。通説の部分がよく分かります。スッキリ。2018/11/23
アキ
51
専門家が分野ごとに最新の知見を示してくれて素晴らしい内容。特に大石学の江戸時代を合理的・文明的な官僚システムと教育によって支えられ250年平和をもたらした時代として世界から見直されつつあるという点が印象に残る。明治は江戸の達成と見るべきと。吉宗が公文書システムを整理し、官僚制の基礎を作った。識字率の高さは戦国時代の兵農分離による文書の流通による。墾田永年私財法は奈良時代の律令を平安時代に国の実情に合わせた肯定的な制度、など見方が変わり興味深い。巻末に日本史をつかむための100冊と内容の紹介がある。良書。2018/11/02
yutaro13
49
積読本。邪馬台国から象徴天皇制まで、日本史を29の論点で辿る。私は高校日本史を選択していなかったので日本史知識にはかなり欠落がある。というわけで、たまにこんな本を読んで補ってやる必要があります(すっと頭に入ってこないところもありますが)。歴史を学ぶことで現代を相対化しようとよく言われるが、歴史研究そのものが既存の研究や歴史観を相対化していく試みの積み重ねなのだろうと思う。巻末の「日本史をつかむための百冊」がありがたい。全てを読むのは無理だけど、興味を持ったところから挑戦したい。2021/03/08
-

- 電子書籍
- 報知高校野球 - 2019年3月号
-
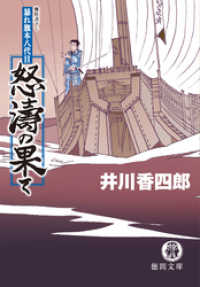
- 電子書籍
- 暴れ旗本八代目 怒濤の果て 徳間文庫