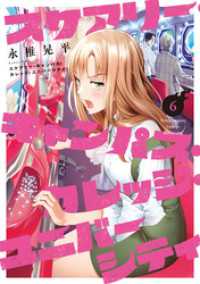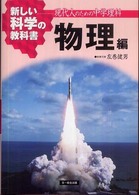- ホーム
- > 電子書籍
- > 絵本・児童書・YA・学習
内容説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
対象年齢:小学生から
生活/歴史/日本文化
・内容紹介
「どうくつぶろ」から、「釜ぶろ」、「秀吉のおふろ」、「湯屋」、「銭湯」まで、私達の生活に欠かせない『おふろ』の歴史を描いた絵本です。美しい古典やまと絵とわかりやすい説明で、見れば見るほどおもしろいおふろが満載! 奈良時代から、現代まで、時代に合わせて様々な姿を見せてくれるおふろから、その時代を生きる人々の生活も感じられる1冊です。
・作/菊地ひと美さんからのメッセージ
毎日のほほんと入っているおふろ。「えーっ、おふろに歴史なんかあったの?」というところでしょうか。……あります。しかも、極めつけに楽しいものなんです。
昔々、日本の海岸に作られはじめた「どうくつぶろ」。奈良時代には、東大寺のりっぱなお寺のような、いえ、どこから見てもお寺にしか見えないおふろがありました。古典やまと絵の情景の中に、昔のえぼしを被った人々が集まっている姿はとても風情があります。
平安時代はどうでしょうか。皇族など高貴なご身分の方々が入るおふろは? かわいい姫君が、白壁に朱の柱のお湯殿で、ゆったりと湯あみをしています。まるで、おとぎ話のような世界です。
そして桃山時代には、豊臣秀吉のおふろが登場。戦乱と桃山のきらびやかな時代のおふろはどんなかたちをしているのでしょうか。
次の江戸時代といえば、「銭湯」です。たらいの中で泣いていて、お母さんを困らすのはどの子でしょう。あーあ、走り回っている子もいます。さてさて長屋の路地裏にも行ってみましょう。「あれっ、なんだって外なのにおふろに入っているの?」
現代のおふろからは想像もつかない、おふろの歴史。昔の絵巻物を見るような、古典やまと絵の世界で描きました。夢見るような楽しいおふろの数々。そして、そこを行き来していた人々と出会ってください。
※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
pino
yomineko@鬼畜ヴィタリにゃん💗
♪みどりpiyopiyo♪
鱒子